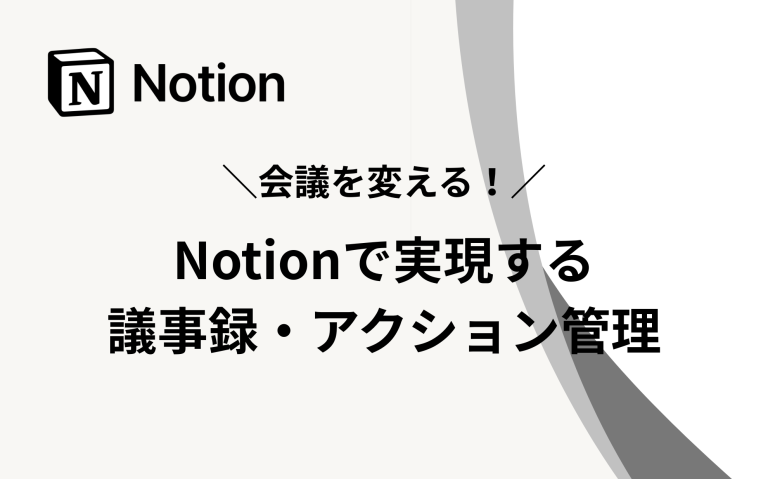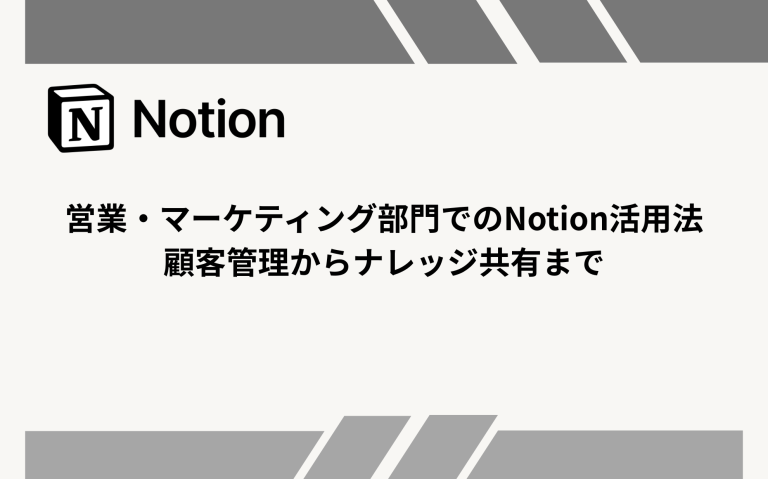成長企業で深刻化する社内問い合わせの「迷子化」──放置すれば起こる混乱と、Jira Service Managementによる解決策
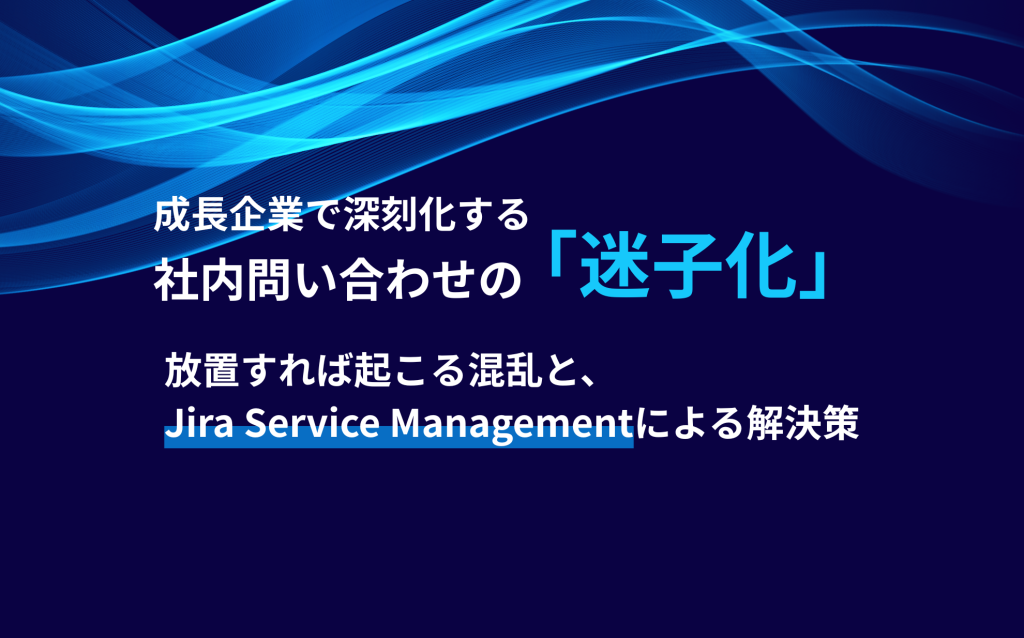
- 執筆者
-
 aslead編集部
aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。
最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。
企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。
急成長企業で爆発的に増える“社内問い合わせの迷子化”現象
事業規模が拡大し、社員数や拠点が増えると、「社内の問い合わせ対応が混乱し誰もが“迷子”になる」現象が顕在化します。
たとえば——
- 「誰に・どこに問い合わせれば正解か分からない」
- 担当部署を探して社内をさまよい歩く
- 各部署が独自に対応した結果、情報がバラバラに属人化する
こうした“迷子化”は、情報システム部門にとって大きな頭痛の種です。人が増えれば問合せも増え、従来の口頭・メール中心の運用では現場が崩壊しかねません。「対応が追いつかない」「たらい回しで現場から不満が噴出する」といった悲鳴も、成長企業では珍しくありません。
【課題の全体像】組織拡大とともに深刻化する「迷子化」の3つの要因
なぜ成長企業は“迷子化”を招きやすいのでしょうか。その背景には、組織や情報管理の急激な変化による3つの主な要因があります。
1. 【窓口の不明確化】
組織が拡大・細分化するほど、「どの部署・誰が窓口なのか」が分かりにくくなります。部署ごとに非公式ルールで独自対応している場合、社員は“部署をたらい回し”されることも。結果、同じ問い合わせでも人によって対応が異なり、大きな非効率と混乱を生み出します。
2. 【情報・ツールの属人化・分散】
成長過程で新規プロジェクトや事業部単位で独自ツール・システムを導入しやすくなります。そのため、「全社のシステムなら情シス」「だが、部署独自ツールは誰が担当?」と迷いが発生。結果、詳しそうな個人への属人的な問い合わせが常態化し、ナレッジやノウハウも部署・担当者ごとに分散してしまいます。
3. 【情報の集約・標準化の遅れ】
急成長の現場では業務フローやドキュメントの整備が後回しになりがちです。最新のマニュアルやFAQが部署ごとに散在し、アップデートされないまま放置されるなど、情報共有が不十分な状態が続きます。そのため、社員は「どこを見れば正しい情報が得られるのか分からず」、結局“人に聞く”非効率な対応に陥りやすくなります。
【構造的なリスク】属人化・情報散在が生む“止まる現場”と“底なしの非効率”
属人化が進むことで発生する深刻なリスクは、単なる効率低下にとどまりません。
- キーパーソン不在=業務停止リスク 「あの人だけがやり方を知っている」状態では、1人休むだけで問い合わせ対応・意思決定がストップ。休暇や退職時の混乱も現実的な問題となります。
- 更新されないマニュアル・FAQ 社内の各所に散らばった文書やFAQ、誰もアップデートしなければすぐに陳腐化。社員は最新情報を探しきれず結局「詳しそうな人」に直接聞くため、同じ質問に何度も個別対応しなければならなくなります。
- 社内ナレッジが共有できず自己解決できない 情報が標準化・共有されていないことで、社員の自己解決力が上がらず、現場への問い合わせ負荷が際限なく増えます。これが現場の“疲弊”と“成長のボトルネック”につながってしまうのです。
ここまでのまとめ——なぜ「迷子化」は成長企業の足かせになるのか?
問合せの“迷子化”は、組織の拡大・多様化がもたらす避けられない課題
- 非効率・属人化・ナレッジ分断が重なることで、業務全体が停滞しやすい
- これを抜本的に解決する仕組み作りが、今や急務**
次章では、このような課題をどのように“標準化・集約・効率化”できるのか——Jira Service Management (以下、JSM) で実現する解決策を、実例とあわせてご紹介します。
Jira Service Managementによる解決アプローチとは
上記のような課題に対し、Atlassian社が提供するJSMは強力なソリューションとなりえます。JSMはもともとITサービスマネジメント(ITSM)を支援するサービスデスクプラットフォームですが、情報システム部門だけでなく人事・総務・法務など あらゆる社内問い合わせを一元管理できる柔軟性 を備えています。ここではJSM導入によって得られる主なメリットを、社内問い合わせの現場目線で解説します。
問い合わせ窓口の一本化による「迷子」の解消
JSMを導入すると、社内の問い合わせ窓口を一本化したポータルを構築できます。 例えば上図のようにIT部門だけでなく、人事・経理・施設管理など各種サービスデスクを一つの「サービスセンター」上に集約し、社員はそこにアクセスすれば必要な問い合わせ先が一目で分かるようにできます。誰に聞けばよいか分からず社内をさまよう必要はもうありません。社員は直感的なセルフサービスのポータルから素早く支援を得られ、問い合わせを受ける各チーム側もJSM上で依頼を受け付けて横断的に管理できるため効率的です。結果として問い合わせ対応の入口が統一され、「どの部署に連絡すべきか分からない」という迷子状態を防ぐことができます。
さらにJSMでは、1つのプラットフォーム上で複数チームの業務を管理できるため、ITサポートから人事・総務系の依頼まで包括的に扱うことができます。社内のどんな種類の問い合わせであっても最初の窓口体験が統一されることで、社員側の利便性が飛躍的に高まります。裏側では適切なチームへチケットをエスカレーションしたり、カテゴリーごとに自動で担当部署に振り分けることも可能なので、問い合わせが誤った部署に飛んでしまったり、たらい回しになるリスクも減少します。このようにJSMは社内問い合わせの「入口」を一本化しつつ、背後では部門横断のサービス提供を支えることで、成長企業にありがちな問い合わせ混乱を収めることができます。
ナレッジポータルで自己解決を促進
JSMの大きな特徴の一つがナレッジマネジメント(知識管理)機能です。Confluenceなど社内Wikiと連携し、よくある質問と回答をナレッジベース(FAQ記事)として蓄積・共有することで、社員が問い合わせを送る前に自己解決できる仕組みを作ります。事実、社内問い合わせの多くはFAQが充実していれば社員自身で解決できる類のものです。JSMでは問い合わせポータル上で関連するナレッジ記事を自動提案することができるため、社員は質問を投稿する前に適切な記事に辿り着きやすくなります。これにより問い合わせの抑止(ディフレクション)効果が期待でき、問い合わせ対応件数そのものを減らすことができます。
ナレッジが蓄積され社内に共有されることは、属人化の解消にも直結します。JSMのナレッジポータルを活用すれば、これまで特定の担当者だけが知っていた暗黙知を明文化して組織全体の財産に変えることができます。ベテラン社員が個人で抱えていたノウハウも記事化されていけば、担当者が不在でも残された記事をもとに他のメンバーが対応できるようになります。実際にJSM導入企業では「ナレッジを管理・共有することで、チームワークが強化され自己解決できる問い合わせが増えた」という声が聞かれます。JSMは単なるFAQツールではなく、問い合わせ対応と知識共有がシームレスに連携する点が強みです。問い合わせ対応と並行して蓄積されるナレッジデータは、今後の社員トレーニングや業務改善にも役立ちます。
問い合わせ対応プロセスの標準化と可視化
属人化した問い合わせ対応を改善するには、対応プロセスの標準化と可視化が不可欠です。JSMはITILベースのワークフローをはじめ、サービス管理に必要な機能を包括的に備えており、組織のベストプラクティスに沿った対応プロセスを標準化するのに適しています。例えば、インシデントやサービス要求など問い合わせタイプごとにテンプレート化されたワークフローや優先度設定、サービスレベル目標(SLA)管理をすぐに利用でき、対応の抜け漏れや遅延を防止できます。手作業や属人的判断に依存していた部分も、JSM上で定義したルールに従って自動化できるため、対応品質の平準化・向上につながります。特にSLA管理機能によって対応時間の目標が明確になり、期限が近づけば自動通知でエスカレーションするといった仕組みで、担当者任せだった対応スピードが組織的にコントロール可能になります。
さらにJSMでは、問い合わせ対応状況をリアルタイムに可視化できるダッシュボードやレポート機能が充実しています。問い合わせの件数や種類、対応に要した時間、各チーム・エージェントごとのパフォーマンス指標などを簡単に集計・グラフ化できます。これにより、これまで属人的な勘に頼っていた部分がデータに基づき把握できるようになり、ボトルネックの特定や業務改善のサイクルを回しやすくなります。実際にJSMへ移行した企業では、「問い合わせ状況が可視化されたことで長時間放置されるチケットがなくなり、対応スピードはもちろんサポート品質も向上した」と述べています。可視化された数値をチーム内で共有すれば、小さな変化にも気付きやすくなり、改善すべきポイントをメンバー全員で議論・対策するといったPDCAも回しやすくなるでしょう。
このようにJSMの導入によって、問い合わせ対応のプロセスが組織全体で共有された標準フローに乗り、対応状況が常に“見える化”されることで、属人化や情報散在によるムダが大幅に削減されます。問い合わせ対応業務そのものがチームで最適化・継続改善される仕組みが整う点は、JSMを導入する大きなメリットと言えます。
明快なコスト体系と導入しやすさも魅力
このように多機能なJSMですが、導入・運用コスト面でも明快で計画を立てやすい点は情報システム部門にとって見逃せないメリットです。JSMのライセンス費用は「エージェント」(問い合わせ対応を行うユーザー)数に対してのみ発生し、問い合わせを行う社員(カスタマー)は何人いても追加費用はかかりません。極端に言えば、社員全員がサービスポータルの利用者になったとしてもコストはエージェント数分だけで済むため、社内サービスデスクを全社規模で展開しやすい料金体系になっています。
実際、前述のDNPのケースでも「ライセンスを持たないユーザーにもアクセス権を付与して問い合わせ状況を共有でき、追加コストを抑えられる点が魅力だった」とされています。このように明確で予測しやすいコスト体系は、成長途上で社員数が増えていく企業にとって安心材料です。他のツールにありがちな「利用者アカウントごとの課金で、利用範囲を広げるほど費用が青天井」といった心配が少なく、必要な部門に順次サービスデスクを拡大してもコスト管理しやすいでしょう。加えてクラウド版であれば初期導入のハードルも低く、短期間でトライアル導入を始められるのもポイントです。総じてJSMは、高機能でありながらコスト面・運用面でもスモールスタートしやすく、将来の拡張にも柔軟に対応できるツールだと言えます。
まとめ:社内問い合わせの混乱を脱却し、建設的なITサービスへ
社内問い合わせ対応の「迷子化」や属人化による非効率は、放置するとビジネス全体の足かせになりかねない深刻な問題です。しかし、適切なツールと仕組みを導入すれば解決への道筋は明確です。JSMを活用することで、問い合わせ窓口の一本化、ナレッジの集約、対応プロセスの標準化・可視化といった施策を一挙に実現でき、情報システム部門として社内サービスの質と効率を飛躍的に高めることが可能になります。
成長を続ける企業の情報システム責任者の方は、ぜひ一度JSMの導入を検討してみてはいかがでしょうか。社内問い合わせ対応を混乱から解放し、生産性向上と社員満足度の向上を両立できるJSMは、次世代のITサービスマネジメント基盤として有力な選択肢です。実際に多くの企業が既にJSMで社内の様々なサービスデスクを統合し成果を上げています。貴社でも同様のメリットを享受できる可能性は高いでしょう。
最後に、本記事をご覧になってJira Service Managementの導入に関心をお持ちになりましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。Atlassian Platinum Solution Partnerであるasleadが、要件整理・初期設計から運用支援、さらにはJira/Confluence連携やナレッジ管理、ユーザートレーニングに至るまでトータルでサポートいたします。ぜひ今すぐ行動に移してみてください。