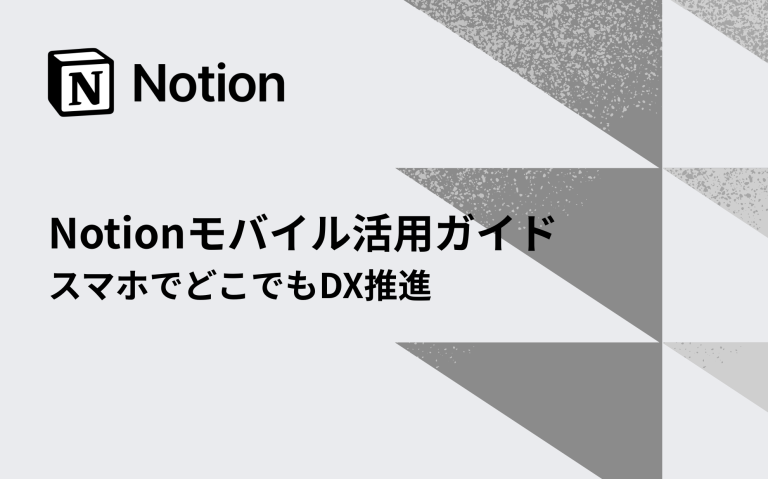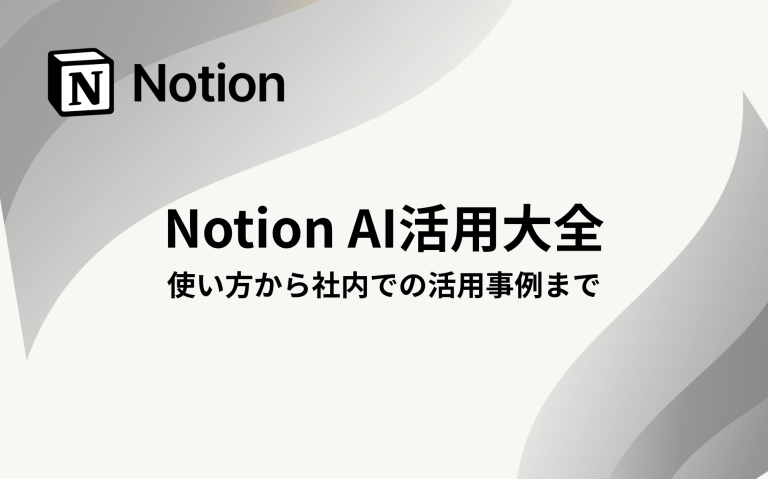Notionアップデート最新動向:知っておきたい新機能とビジネス活用
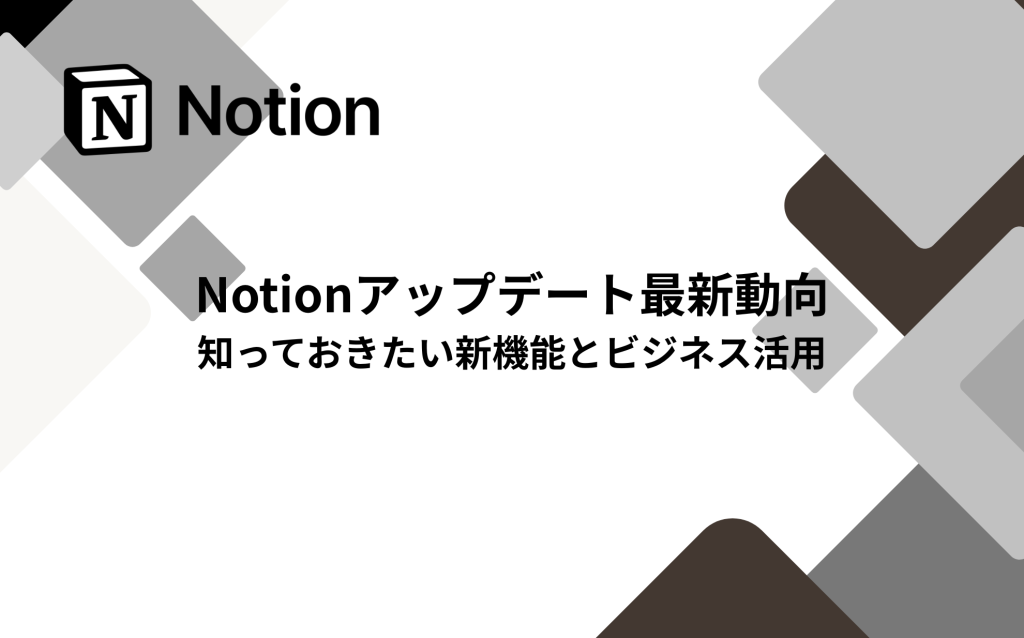
- 執筆者
-
 aslead編集部
aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。
最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。
企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。
はじめに
業務管理ツール「Notion」は2025年以降、AI統合からデータベース機能、コラボレーション、セキュリティまで大幅なアップデートを重ねています。IT部門やDX推進担当者、現場マネージャーの皆様に向けて、最新のNotion新機能・改善点を整理しました。生成AIの活用やデータ管理性の向上、チーム連携強化、さらには企業向けのガバナンス対応まで、社内DX促進に役立つポイントを網羅します。記事の最後にはこれら機能の導入相談先もご案内しています。
Notion AIの強化 – 業務効率を飛躍させるAI機能
2025年のアップデートでNotionに深く統合されたAI機能(Notion AI)は、日々の業務生産性を大きく向上させます。ここでは主要なAI新機能を紹介します。
AIミーティングノートによる議事録の自動化
会議内容の記録はNotion AIに任せましょう。AIミーティングノート機能により、会議の音声をリアルタイムで文字起こしし、終了後には内容を自動要約してくれます。重要なアイデアや決定事項を漏らすことなく保存し、後からキーワード検索で素早く参照・共有可能です。担当者が逐一メモを取る手間を省き、会議後のフォローアップも効率化します。
エンタープライズサーチと外部ツール連携
情報検索の手間も大幅に削減。エンタープライズサーチでは、従来比3倍以上の外部アプリから社内ナレッジを横断検索できます。現在はSlackやGoogleドライブ、GitHub、Jira、Microsoft Teams/SharePoint/OneDrive等に対応し、間もなくLinearやGmail、Zendesk、Salesforce、Boxにも対応予定です。さらにPDFや他のNotionデータベース内の内容まで検索可能となり、社内外に散在する情報をNotionから一括で探し出せます。「答え探し」の時間を短縮し、必要な情報へ即アクセスできる環境が整いました。
リサーチモードによるレポート自動作成
調査資料やレポート作成もAIがサポートします。新しいリサーチモードでは、Notionワークスペース内の全データや連携ツール、さらにはWeb上の最新情報まで分析し、詳細なレポートを数分でドラフトします。プロジェクト振り返りや市場調査、ベストプラクティス集なども、AIが下調べから文章化まで自動でこなすため、担当者の工数を大幅に削減できます。「社内アナリスト」としてNotion AIを活用することで、意思決定に必要な資料作成が迅速化されるでしょう。
AIホームと最新モデルへのアクセス
Notionのサイドバーには「AIホーム」タブが新設され、AI機能へのアクセスが容易になりました。ここから自然言語で質問したり、リサーチモードを起動したり、カスタムワークフローを作成したりできます。またChatGPTや Claude などの最新のAIモデルも組み込まれ、アプリ間の切り替え不要で直接対話可能です。追加費用や別契約も不要で、用途に応じてモデルを選択できるため、ブレインストーミングから専門文書の下書きまで幅広くAIを活用できます。
ビジネスプランでのAI無制限利用
2025年5月より、Notionの料金プランも刷新されました。Businessプラン・EnterpriseプランではNotion AIが標準搭載となり、上記のエンタープライズサーチやAIミーティングノート、リサーチモード等の高度なAI機能を回数無制限で利用可能です。従来は追加課金が必要だったAI機能がプラン内に含まれるため、利用コストを気にせずチーム全員がAIの恩恵を享受できます。企業としてAIファーストな業務環境を整える大きな追い風となるでしょう。
データベース操作性の向上 – 情報管理の効率化
Notionのデータベース機能もこの期間で格段に強化され、現場での情報入力・整理がより直感的になりました。フォーム入力やレイアウト自由度、ワークフロー自動化など、IT部門に嬉しい機能改善を見ていきます。
Notionフォームと条件分岐による現場データ収集
社内アンケートや申請フローもNotionで完結できます。2024年末にフォーム機能がNotion本体に新搭載され、外部ツール不要でリクエスト収集やフィードバック収集が可能になりました。さらに2025年3月には条件分岐機能が追加され、回答内容に応じて後続の質問項目を出し分ける高度なフォームも作成できます。例えば「問い合わせ種別で『技術的質問』を選んだ場合のみ詳細項目を表示」といった分岐が設定可能です。この条件付きフォームはBusinessプラン以上で利用できますが、Googleフォーム等に頼らずNotionデータベースに直接繋がる入力フォームを構築できるのは大きなメリットです。現場からのデータ収集をスムーズにし、回答はそのままデータベースに整理・蓄積できます。
データベース自動化機能: 定期タスク・外部連携・計算の効率化
繰り返し発生するタスクや通知はNotionのオートメーション機能に任せられます。定期レポート作成やリマインダー送信など、スケジュール実行型の自動処理が可能になりました。例えば毎週の会議アジェンダページを自動生成したり、プロジェクト進行中のステータス報告を所定の曜日に自動更新させる、といったことが「定期実行オートメーション」で実現できます。また、トリガー条件に応じてメール通知を自動送信する機能も搭載されました。フォーム経由の申請受領時やデータベースのステータス変更時に、Gmail経由で担当者へ通知メールを飛ばすことができます。さらにはWebhook連携にも対応し、Notion内の変更を外部システムとリアルタイム連動可能です。例えば「ブログ記事のNotionページを公開と同時に社内サイトに反映」「タスク更新時にZendeskで顧客対応チームへ連絡」といった連携がシームレスに行えます。加えて、ボタンやデータベーストリガーで数式計算を自動実行する機能も強化されました。完了したタスクの所要時間を自動計測・記録する等、バックグラウンド計算も自動化でき、定型業務の省力化が進みます。これら自動化機能により、手作業のミス削減と業務プロセス全体の効率化が期待できます。
ページレイアウトとビューの改善 – 柔軟な情報整理
各チームやプロジェクトに合わせて情報を見やすく整理できるよう、ページレイアウト設定やビュー機能もアップデートされました。データベースの項目配置を自由にカスタマイズできるレイアウト機能が追加され、タスクや目標、文書などを使いやすい形でレイアウトできます。ページ上部の「Customize layout」からレイアウト編集が可能になり、情報をカード形式で並べたり、2カラム表示にしたりと柔軟なページ設計ができるようになりました。さらに一つのページ上で複数のデータベースをタブ切替表示できるようになったのも注目ポイントです。プロジェクト管理ページに「タスクリスト」「バグ管理」「ロードマップ」など複数DBを集約し、タブで素早く切り替え参照できるため、関連情報のダッシュボード化が進みます。グラフ表示も改善され、チャート上の任意の部分をクリックすると元データの詳細をワンクリックで表示できるようになりました。これによりレポート上の数値から直接データベース項目を確認し、分析や追跡調査をスピーディに行えます。視覚的な把握と詳細データの確認がシームレスに繋がり、現場マネージャーにとって意思決定に役立つUI改善といえます。
AIを活用したデータベース構築支援
データベースをゼロから設計する手間も、Notion AIが大幅に軽減します。「/database」コマンドのAIビルダー機能により、作りたいデータベースの概要を文章で伝えるだけで、自動的にプロパティ(項目)やビューが整ったデータベースが生成されます。人手なら数十分かかるセットアップも、AIがわずか30秒ほどで完了し高品質なテーブルを用意してくれるため、ナレッジ整備のスピードが飛躍的に向上します。IT部門でテンプレートを用意しなくとも、各現場が自分たちの用途に合わせたデータベースをAI補助で手軽に作成できるようになりました。
※なおこれら新機能の追加に対して、Notion開発チームはパフォーマンス最適化も並行して実施しています。
チームコラボレーション機能の拡充 – 情報共有とコミュニケーションの強化
社内の連携力を高めるための機能も強化されています。Notionは単なるドキュメント作成に留まらず、メールやスケジュール管理、ドキュメント共同編集まで一元化し、チーム全体の生産性を底上げします。ここではコラボレーションを促進する主なアップデートを解説します。
「Notionメール」とカレンダー連携によるコミュニケーション一元化
ついにメールクライアントまでもNotion内に統合されました。2025年に発表されたスタンドアローン型の「Notionメール」は、Gmailアカウントと同期して動作する画期的なメールアプリです。従来の受信トレイ概念を刷新し、ユーザーの業務フローに最適化されたカスタムビューやレイアウトでメールを整理できます。例えばプロジェクト別・優先度別にメールを自動振り分けするビューを作成し、関連するメールだけをまとめて表示するといったことが可能です。Notionデータベースのビューと似た操作感で、フィルターやグルーピングを駆使しながら自分やチームに合った受信トレイをデザインできます。さらにNotion AIもメールに深く組み込まれており、あらかじめ設定したプロンプトに基づいて受信メールの自動ラベル付け・仕分けやメール文面の下書き生成、アーカイブ整理までも行ってくれます。Notion上でそのままスラッシュコマンドによるブロック挿入やスペースキーでAI呼び出しができるため、ドキュメントと同様の感覚で美しいメールを書ける点も特徴です。加えてスケジューラー機能との連携もシームレスです。Notion上でメール本文作成中に「/schedule」コマンドを入力すれば、自分の空き時間候補を埋め込んで相手に共有でき、会議の日程調整を往復メールなしで完結できます。共有リンクはNotionカレンダーと連動し、相手が希望の時間を選べば自動で予定が確定します。これらによりメール対応や日程調整にかかる時間を大幅短縮でき、コミュニケーション業務の効率化と情報一元管理が実現します。
ドキュメント共同編集: 提案モードとコメント管理の強化
チームで1つの文書を編集する際の煩雑さも、Notionの改善で解消しつつあります。まず、Googleドキュメントの「提案モード」に相当する「サジェスト(提案)機能」がNotionに導入されました。共同編集者は直接ページ内容を修正する代わりに提案として変更を追加でき、最終承認者はそれらをワンクリックで承認または却下できます。誰がどこを編集提案したか履歴が残るため、従来課題だった「いつの間にか内容が書き換わっていた」という事態を防ぎつつ、編集フローをスムーズにしました。また、コメントによるフィードバック管理も強化されています。Notionの通知Inboxがアップデートされ、提案箇所やコメントがスレッド形式で見やすく整理されました。ページをまたいでコメントを処理しても、この新しいInboxパネルは画面横に常時表示され続けるため、複数ページにわたるフィードバック対応も漏れなく行えます。メンション付きコメントで担当者に通知を送り、ディスカッションしながらドキュメントを推敲する作業がより直感的かつ効率的になりました。リアルタイム共同編集+提案モード+コメント管理の組み合わせにより、チーム文書の質を保ちつつスピーディに仕上げることが可能です。
ナレッジ共有と情報可視化: Wiki強化・ページ検証・ダッシュボード化
組織内ナレッジを活用する仕組みも進化しています。Notionは部署Wikiやマニュアルの作成・共有に適したプラットフォームですが、新たに「ページ検証(ベリファイ)機能」が加わりました。これは重要なWikiページを管理者や専門家が「公式に検証済み」マークを付与できる機能で、検証済みページは社内検索結果で優先表示されたり、他ページからのメンション時に明示されたりします。一定期間経過後には再検証を促すリマインダーも出るため、情報の鮮度も保たれます。この機能により、社内ドキュメントの信頼性と最新性を担保し、現場が安心して参照できるナレッジ基盤を構築できます。加えて前述の複数データベースのタブ表示機能もナレッジダッシュボードに応用可能です。部署横断の指標やプロジェクト状況を一つのページに集約し、タブで切り替え閲覧することで、分散しがちな情報を一画面で俯瞰できます。たとえば「営業指標」「顧客フィードバック」「開発ロードマップ」を各データベースから引き出し、一元ダッシュボード化すれば、マネージャー層の迅速な意思決定に寄与するでしょう。さらに2024年にはNotion Sites機能も導入され、社内ページをそのまま外部公開Webサイトとして発信することも容易になりました(社外向けナレッジ共有)。このように、社内外への情報共有と可視化がより柔軟かつ強力になっています。
外部ツールとの連携強化 – ワークフローの統合
Notionは他の業務ツールとの連携も年々深化しています。前述のエンタープライズサーチによる他ツール横断検索に加え、JiraやAsanaなど他プラットフォームとのデータ統合も強化されました。2024年にはJira同期機能のアップグレードにより、プロジェクト・課題の双方向同期が高速化しカスタマイズ性も向上しています。またAsanaインポート機能も改善され、選択したプロジェクトをワンクリックでNotionデータベースへ変換できるようになりました。これにより、プロジェクト管理をNotionに集約しつつ既存のデータも無駄にしません。さらにSlack通知との連携や、Teams会議の自動要約(AIミーティングノート)共有など、コミュニケーション系ツールとの統合も進んでいます。各種SaaSが乱立する中、Notionをハブに情報のサイロ化を防ぎワークフローを一体化できる点は、DX推進担当にとって大きな魅力です。
セキュリティとガバナンス対応 – エンタープライズ利用への安心感
企業でNotionを本格導入するにあたり、懸念となるセキュリティ・管理面の機能も充実が図られました。組織全体の管理機能や権限制御、監査・コンプライアンス対応など、IT統制の要求に応えるアップデートポイントを確認します。
組織管理コンソールとガバナンス機能の強化
Enterpriseプランでは、複数のNotionワークスペースを跨いで組織全体の設定を管理できる統合管理コンソールが提供されています。管理者(オーナー)は一箇所でメンバーやゲストの権限設定、セキュリティポリシーを一括管理でき、組織規模でのガバナンスが容易になりました。2025年のアップデートでは特に、社員による非承認ワークスペース利用を制限するポリシー設定が追加されています。社内ネットワーク上でアクセス可能なNotionワークスペースを管理者が制御でき、個人アカウントでの機密データ持ち出しを防ぐ仕組みです。たとえば会社支給PCから社外のNotionワークスペースにアクセスさせない、といったポリシーを設定でき、業務データの流出リスク軽減に繋がります。
シングルサインオン(SSO)とユーザープロビジョニング対応
認証・ユーザー管理の面でもエンタープライズ向け機能が整っています。NotionはOktaやAzure ADなど主要なSSOプロバイダーと連携したシングルサインオンに対応し、社員は社内認証でNotionにシームレスログイン可能です。加えてSCIMプロビジョニングにより、入社・退社時のユーザーアカウント自動登録/削除やグループ連携も行えます。2025年にはログインの利便性向上策として、生体認証デバイス(パスキー)によるサインインもサポートされました。指紋認証やWindows Hello、Touch IDなどを用いたパスワードレス認証で迅速かつ安全にログインできます。併せてNotionカレンダー等の関連アプリとも認証情報が統合され、一度のログインで各サービスを横断利用できるようになっています。こうした機能強化により、社内認証基盤との統合運用やユーザーデータの一元管理がスムーズに実現できます。
コンテンツの信頼性確保と監査ログ
情報統制の観点では、前述のページ検証機能が社内コンテンツの信頼性を高めています。公式に承認されたページが明示されることで、利用者は安心して最新正確な情報を参照可能です。またEnterpriseプランでは監査ログ(Audit Log)機能が提供され、ワークスペース内で発生した各種イベントの履歴を管理者が確認できます。ページ閲覧や編集、共有設定の変更、アカウント操作など幅広いアクティビティをエクスポート可能で、不審な挙動の調査やセキュリティインシデント発生時のトラブルシュートに役立ちます。さらにコンテンツ検索(Content Search)では、全ページの公開状況や共有範囲を一覧でき、組織内の公開ポリシー遵守状況を監視できます。例えば「外部共有されているページの洗い出し」「誰がどのページにアクセス可能か」を管理者が把握でき、過剰な情報公開を是正するといったガバナンス対応が取れます。加えてNotionは主要なセキュリティ基準への準拠(SOC2 Type II取得など)やデータ暗号化(保存・転送時)、外部DLP/SIEM連携など企業セキュリティ要件にも応えています。これらの仕組みにより、クラウド上でも機密情報の適切な保護と内部統制の実施が可能となり、大企業でも安心してNotionを活用できる基盤が整っています。
まとめ – Notionの進化をDX推進に活かすには
以上、2025年以降に追加・改善されたNotionの新機能を、企業内活用の視点でご紹介しました。強力になった生成AIは情報整理や文書作成の時間を劇的に短縮し、データベース機能の向上で現場の情報活用が円滑化します。加えてメール・カレンダー統合や提案モードによりチームコラボレーションが効率化し、セキュリティと管理機能の充実で全社導入への不安も払拭されました。それぞれのアップデートは単体でも効果的ですが、Notionというオールインワンのワークスペース上で連携し合うことで、企業のデジタルトランスフォーメーションを強力に後押しします。ぜひこの機会に最新のNotionを活用し、社内の情報共有や業務プロセス改革に役立ててみてください。
お問い合わせ・導入のご相談
弊社ではNotionのエンタープライズ導入支援や社内展開のご相談を承っております。今回ご紹介した新機能の詳しい活用方法や、企業向けプランへの移行検討についてなど、お気軽にお問い合わせください。専門スタッフが貴社のDX推進をサポートいたします。