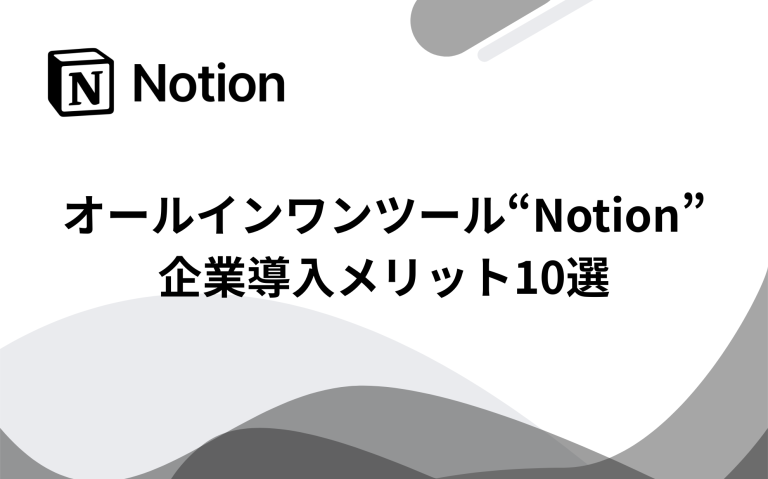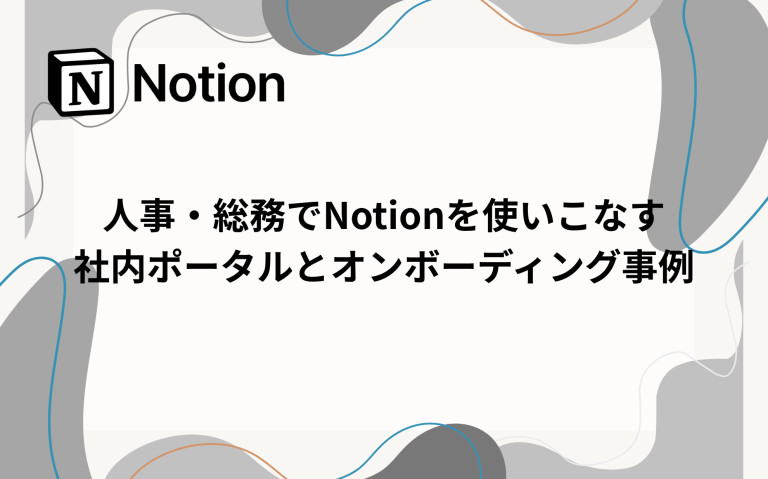Notion と Confluence: モダンなナレッジ管理ツール徹底比較
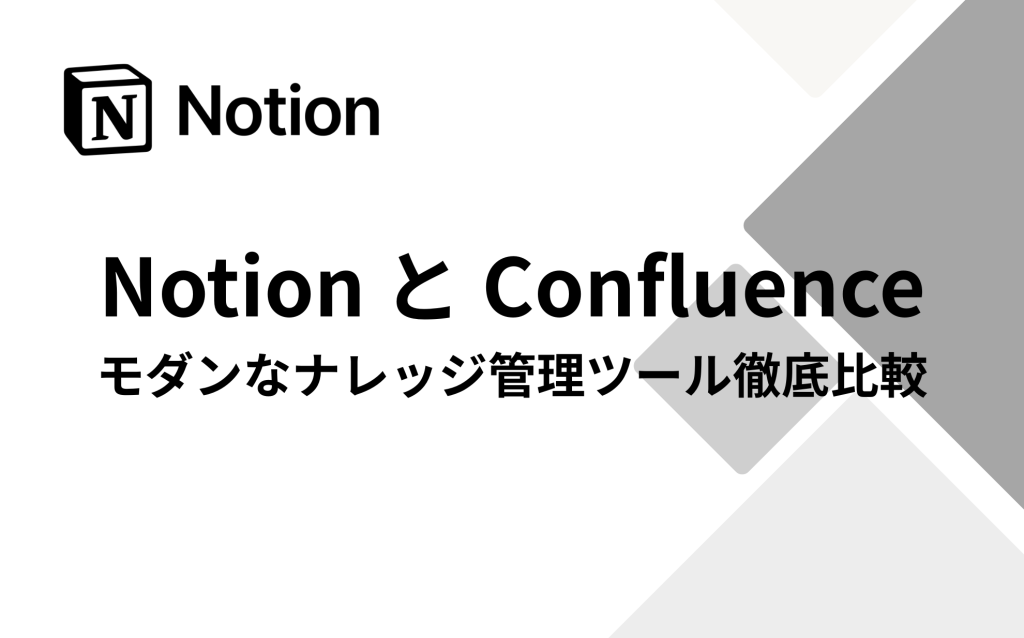
- 執筆者
-
 aslead編集部
aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。
最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。
企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。
現代の企業では、情報共有やナレッジ管理のツール選定が組織の生産性に大きく影響します。特に注目されるのがNotionとConfluenceの2つのツールです。本記事では、両者の特徴や強み、適した活用シーンの違いを比較し、組織にとっての最適な選択を検討します。
両ツールの概要と市場での位置付け
まずはNotionとConfluence、それぞれの基本概要と市場での位置付けについて押さえましょう。
Notionとは?概要と市場での立ち位置
- Notion(ノーション)は2016年に公開された比較的新しいオールインワンのコラボレーションツールです。もともとは個人ユーザーや小規模チーム向けに設計され、メモ作成、タスク管理、データベース管理、カレンダーなど多彩な機能を1つのアプリケーションで提供する点が特徴です。直感的でシンプルなインターフェースと高度なカスタマイズ性を備えており、小規模チームや個人の生産性向上ツールとして急速に人気を博しました。実際、Notionの柔軟性は非常に高く、Wikiの作成からプロジェクト計画、会議メモの整理、新入社員のオンボーディング資料作成まで幅広く活用されています。その汎用性ゆえにユーザーが自在にワークスペースを作り込める反面、後述するように情報が増えた際の整理には工夫が必要とされます。
Confluenceとは?概要と市場での立ち位置
- Confluence(コンフルエンス)はAtlassian社が2004年にリリースしたエンタープライズ向けのコラボレーション/wikiプラットフォームです。チームや組織単位でのドキュメント作成やナレッジ共有に焦点を当てたツールで、プロジェクトの進行状況管理や会議議事録、技術文書の蓄積などで広く利用されています。長年にわたり信頼性の高いチームコラボレーションツールとして多くの企業で採用されており、2024年時点で世界中で75,000以上のユーザー(企業/チーム)に利用されているとの報告もあります。Confluenceは「スペース」と呼ばれる単位で情報を整理し、組織的にコンテンツを蓄積できるのが特徴です。特にソフトウェア開発組織ではJiraなどプロジェクト管理ツールと連携したナレッジ基盤として定評があり、エンタープライズ規模でのナレッジ管理に適した構造と機能を備えています。
市場ポジションの違い
NotionとConfluenceはそれぞれ狙うユーザー層や得意分野が異なります。一般に、Notionは個人利用や小規模チームでの利用が多く、その柔軟性と豊富な機能によりタスク管理から文書管理まで一手にこなす「万能ツール」という位置付けです。一方でConfluenceは大規模チームや企業全体でのナレッジ共有に適した「組織向けの情報プラットフォーム」として位置付けられています。実際Atlassian社も「Notionは個人の生産性向上に限られている」のに対し、「Confluenceはチームワークの自然な流れを支える複数のコンテンツタイプを備えたコネクテッドなワークスペース」であると述べています。もちろん近年ではNotionも有料プランを通じてエンタープライズ機能を強化し大企業での導入例も増えていますが、歴史的経緯からNotionはボトムアップ志向、Confluenceはトップダウン志向のツールと捉えられることが多い傾向があります。次章では、具体的な機能面での比較を観点別に見ていきましょう。
比較観点別の機能と特徴
ここでは操作性、検索性、情報構造化のしやすさ、セキュリティ、拡張性、他ツール連携、エンタープライズ向け機能といった主要な観点で両ツールを比較します。それぞれの項目で両者にどんな違いがあるのか整理してみます。
操作性(UIや編集機能の使いやすさ)
Notionの操作性は直感的で、一般的に習得のしやすさで高く評価されています。ドラッグ&ドロップ中心のブロックエディタを採用しており、文章、画像、チェックリスト、コードスニペットなど多様な要素を自由にレイアウトできます。必要な機能はキーボードから「/」スラッシュコマンドで呼び出せるため、慣れれば高速にページを構築可能です。テンプレートも用意されていますが数は絞られており、かえって必要なテンプレートを迷わず選べる利点にもなっています。一方で機能が豊富すぎるがゆえに初見ではどこから手を付ければ良いか戸惑うケースもあり、「できることが多すぎて圧倒される」との指摘もあります。しかし総じてプログラミング知識のない非エンジニア層でも扱いやすく、学習コストの低いツールと言えます。
ConfluenceはWikiスタイルのリッチテキストエディタを備え、あらかじめ用意されたメニューやボタンから機能を利用できるため、操作はシンプルです。ページ上部に編集オプションが並んでおり、ユーザーはテンプレートを選んだり段落や見出しのスタイルを指定したりと、Wordに近い感覚でドキュメントを作成できます。標準で多数のテンプレート(議事録、製品要件、仕様書など)が用意され、必要に応じて追加のマクロ(埋め込み機能)も利用可能です。Notionに比べるとUIはやや業務システム的で「若干複雑」と感じる向きもありますが、ナビゲーションの構造が明確で、スペース内のページツリー表示などにより組織内のコンテンツを見通しやすくなっています。また複数人が同時に編集している場合はユーザーアイコンが表示されリアルタイムで変更が同期されるなど、コラボレーション時の挙動もわかりやすいです。
検索性(情報検索のしやすさ)
Confluenceの検索機能は社内Wikiツールの中でも充実している部類に入ります。ページタイトルや本文中のキーワード検索はもちろん、ページに付与したラベル(タグ)による検索やフィルタリングが可能です。また、PDFやOfficeファイルなど添付ファイル内の文字列まで全文検索できるため、大量のドキュメントからでも必要な情報を素早く見つけ出せます。検索結果でキーワードがハイライト表示されるなどの細かな工夫もあり、情報量が多くなっても探しやすい設計です。
Notionの検索機能も基本的なキーワード検索には対応しており、小規模な利用範囲であれば問題なく機能します。しかしConfluenceにあるようなタグ付け機能や階層フォルダによる分類を前提とした検索は苦手です(NotionにはConfluenceのラベルに相当する仕組みはなく、テキストにハッシュタグを書く程度の代替となります)。また、埋め込んだPDF等の添付ファイル内テキストは検索対象になりません。そのため、ドキュメント数や種類が増えてくると目的の情報を探し出すのに時間がかかるケースがあります。もっともNotionではデータベース機能を活用してカスタムなテーブルビューやフィルタを用意すれば、独自の検索・絞り込みも実現可能です。規模が大きくなるほどConfluenceの豊富な検索オプションが頼もしく、一方で小規模ならNotionのシンプル検索で十分、といった使い分けが考えられます。
情報構造化のしやすさ(ナレッジの整理手法)
ナレッジを組織的に蓄積・整理する上で、各ツールが提供する情報構造の枠組みにも違いがあります。
Confluenceでは、まず組織やプロジェクト単位に「スペース」を作成し、その中に階層構造のページを作っていくモデルです。スペースごとに目的や担当部署を分けることでクローゼットにカテゴリ別に書類を収納するようにコンテンツを整理できます。ページはツリー構造で親子関係を持てるため、例えば「プロジェクトA」というスペース内に「要件定義」「設計」「テスト」など階層を作り、その中に各種ドキュメントを配置するといった体系的なナレッジ集積が可能です。古いページをアーカイブする機能も備わっており、情報が陳腐化した場合でも最新コンテンツを優先的に検索・参照できるよう工夫されています。このようにConfluenceは最初から情報を構造化して整理しやすい仕組みが用意されているため、大規模組織でもスケールしやすいと言えます。
Notionの場合、トップレベルに「ワークスペース」があり、その中に自由にページやデータベースを作成していく形になります。近年Notionもビジネス向けに「チームスペース」機能(特定チームだけでページを共有できるセクション)を導入し、コンテンツの区分管理を強化しつつあります。しかし基本的にはページ同士を好きなだけネスト(親子入れ子)できる柔軟性がある分、明確な運用ルールを設けないと情報が散逸しがちです。例えば組織全体で統一された階層ルールがないと、同じような内容のページが複数の場所に作られて重複したり、どこに何があるかメンバーによって構成が異なるといったことも起こりえます。Notionは使い手の発想次第でフォルダ的にもタグデータベース的にも使える反面、情報整理のガイドラインは利用者側で設定する必要があるでしょう。裏を返せば、自由度の高さゆえに組織文化に合わせたカスタムなナレッジ体系も構築できるので、小回りを利かせたいチームには魅力です。
なおNotionには「ページオーナー」や「ページ有効期限」といった独自の知識管理機能もあります。各Wikiページに責任者(オーナー)を設定し、その人物が内容の正確性を担保する仕組みで、必要に応じて情報の有効期限(更新が必要になる目安日)を登録できます。閲覧者はページに表示された有効期限を確認し、期限切れの情報には注意を払うことで情報の鮮度を判断できます。このような機能はConfluenceには標準ではありません(運用ルールや手動対応でカバーする必要があります)。組織のナレッジが陳腐化していく問題へのアプローチとして、Notionは新しい発想での解決策を提示していると言えます。
セキュリティと権限管理
企業利用においてはアクセス権限やセキュリティ面も非常に重要です。この点でも両ツールに考え方の違いがあります。
Confluenceはエンタープライズ向けらしく細かな権限設定が可能です。前述のスペースごとに閲覧・編集権限を設定でき、各スペースに専用の権限セットを持たせることで「部署Aのスペースは部署Aメンバーのみ閲覧可」「機密プロジェクトのページは特定ユーザーのみ編集可」といった制御ができます。さらに各個別ページ単位でも閲覧・編集の制限(ページリストリクション)をかけることが可能で、組織階層やプロジェクト機密度に応じた多段階のアクセスコントロールを実現します。加えて、Confluence(Atlassian Cloud版)では他のAtlassian製品と共通の組織管理機能(Atlassian Access)を利用して、シングルサインオン(SSO)や2要素認証、ユーザー一括プロビジョニング、IP許可リストなど高度なセキュリティ統制を行うことも可能です。オンプレミス版(Data Center版)を自社サーバーに構築すれば社内ネットワーク内に閉じた運用もでき、機密データをクラウドに置けない要件にも対応できます。
Notionもビジネス利用に耐えうるセキュリティ機能は揃えていますが、Confluenceに比べるとシンプルです。Notionでは基本的にページ単位でアクセス共有設定を行います。ワークスペース内のページはデフォルトではメンバー全員が閲覧・編集できますが、ページごとに閲覧者を限定したり、逆に社外ゲストを招待したり、リンクを知っている人だけが読める公開ページにするといった柔軟な共有が可能です。ただし専用スペースごとの権限分離といった機能は持たず、階層構造で親ページに設定した権限が子ページに継承される仕組みになっています。結果としてConfluenceほど細かいアクセス制御はできず、情報公開範囲の管理においてはシンプルなモデルです。セキュリティ面ではNotionもEnterpriseプランでSAML SSO対応や監査ログ提供、コンテンツのエクスポート・バックアップ機能などを提供しており、大企業の要件にも応えつつあります。しかし情報管理ポリシーの細かさや運用上の統制では、長年エンタープライズ利用されてきたConfluenceに一日の長があると言えるでしょう。
拡張性とカスタマイズ
組織によって必要とする機能は様々です。そのための拡張性(プラグインやアドオンによる機能追加、カスタマイズ性)は重要な比較ポイントです。
Confluenceは非常に高い拡張性を誇ります。Atlassian社はConfluence向けに専用のマーケットプレイスを用意しており、無料・有料合わせて数千種類に及ぶアプリやプラグインが提供されていま。例えば社内Wikiを充実させるためのFAQ管理プラグインや、ページにガントチャートや設計図を埋め込むためのアドオン、UIを日本企業向けにカスタマイズするテーマなど、用途に応じて機能を追加できます。自社開発のJiraやTrelloなどとの親和性は言うまでもなく、サードパーティ製も含め3000以上の外部ツールと連携できるエコシステムが確立されています。APIも公開されているため、自社システムとの連携や自動化スクリプトの作成も可能です。このようにConfluenceは「できないことを後から補う」**体制が整っており、特殊なニーズにも応えやすいのが強みです。
Notionは軽量な設計ゆえにConfluenceほどの拡張プラグイン市場はありませんが、その分APIや連携サービスを活用したカスタマイズが行われています。Notion公式のマーケットプレイスはありませんが、ZapierやMake(旧Integromat)といったノーコード連携サービスを使えば、他のSaaSとデータをやり取りしたりトリガー連動したりすることが容易です。また2022年に公開されたNotion公式APIにより、自社システムからNotionのページやデータベースを操作する統合も可能になりました。例えば営業データベースにレコードが追加されたらNotion側に自動でページを生成する、といった業務フローの自動化も工夫次第で実現できます。さらにコミュニティによるカスタムウィジェット(天気予報やカレンダーガジェットをページに埋め込む)やスクリプト拡張も多数公開されており、Notionもまたユーザー主導で柔軟に機能拡張できるプラットフォームと言えるでしょう。ただしプラグイン一つインストールするだけで機能が増えるConfluenceとは異なり、Notionで高度な拡張をするには一定の技術知識や外部サービス利用が必要になる点は認識しておく必要があります。
他ツールとの連携
日々の業務で使う他のツールとの連携性も見逃せないポイントです。これは前述の拡張性とも関連しますが、標準機能として用意されている連携や他システムとの統合の容易さという観点で比較します。
ConfluenceはAtlassian製品ということもあり、同社のJiraやTrelloとの連携がシームレスに行えます。Confluenceのページ上でJiraのチケットを参照・作成したり、Trelloのボードを埋め込んでリアルタイムに編集するといったことが可能です。さらに前述のマーケットプレイス経由でSlackやMicrosoft Teams、Google Drive、GitHubなど主要な業務ツールとの連携アプリが公式・非公式に多数提供されています。例えばSlackからConfluenceページの更新通知を受け取ったり、Confluence上でGoogleドライブ内のファイルをプレビュー表示することも容易です。社内で使っているツール群をConfluenceと結び付けることで、「ナレッジ基盤をハブに業務ツールをつなぐ」ような活用も可能です。実際、Confluenceを導入している企業ではプロジェクト管理やチャット、スケジュール管理などと組み合わせてナレッジを有効活用しているケースが多く見られます。
Notionも近年様々な他サービスとの連携を強化しています。Notionページには標準でGoogleマップやFigmaデザイン、Youtube動画、各種TweetなどをURLを貼るだけでインライン埋め込みできる機能があり、情報集約のハブとして機能します。Slackとも公式連携があり、コメントや@メンションの通知をSlackチャンネルに飛ばすことも可能です。さらにカレンダーやタスク管理ツールとの間接連携(例えばGoogleカレンダーの予定をNotion上に同期表示、あるいはNotionのデータベースをTeams経由で参照など)も外部サービスを使って実現できます。標準機能だけ見るとConfluenceほど他システムとの直接統合は多くありませんが、API公開以降は有志によるコネクタやスクリプトが数多く登場し、工夫次第であらゆる業務データをNotionに集約・連動させられる柔軟性があります。Confluenceが「用意された統合」を使うアプローチなら、Notionは「自分たちで統合を作り込める」アプローチと言え、その点も組織の方針によって向き不向きが出るでしょう。
エンタープライズ向け機能
大企業で利用する際に必要となるエンタープライズ機能についても確認します。具体的にはユーザープロビジョニングや監査、SLA、サポート体制などです。
Confluenceはエンタープライズ利用を前提に長年改良が続けられており、この分野での安心感は高いです。例えばユーザー管理では、Active DirectoryやAzure ADと同期して社内の人事異動に合わせ自動でユーザー権限を更新したり、グループ単位でアクセスコントロールすることができます。また操作ログの記録・監査機能も充実しており、誰がいつどのページを閲覧・変更したかを追跡可能です。データのバックアップ/リストア機能も提供され、万一の際のリカバリ計画を立てやすくなっています。さらにAtlassian社のEnterpriseサポートを契約すれば、重大なトラブル時の優先対応やシステムヘルスチェックなど、大規模導入を支える支援が受けられます。加えて、データセンター版を使えばクラスタ構成による高可用性やオンプレミス環境での利用も可能で、金融機関等の厳しい要件にも応えています。
Notionもエンタープライズプランを用意しており、SAML対応のシングルサインオン、ユーザープロビジョニング(SCIM)による自動ユーザー管理、監査ログのダウンロード、コンテンツ権限の一括管理などをサポートしています。99.9%の稼働率を保証するSLAも提供しており、大規模環境への配慮は年々強化されています。特筆すべきはNotionのシンプルさを維持したままエンタープライズ機能を拡張している点で、例えば先述のページオーナー機能や有効期限設定などは「現場のユーザーが自主的に情報品質を保つ」ための仕組みとして企業利用を意識した追加機能です。もっとも、サービス提供形態は完全クラウドSaaS型のみであり、企業内データセンターに閉じた運用はできません。そのためデータ所在地の規制や厳格なオフライン環境での利用が求められるケースではNotionは選択肢から外れる可能性があります。一方で海外拠点を含むグローバルな企業では、ブラウザさえあればどこからでもアクセスできるSaaS型のNotionは展開スピードの速さという利点もあります。
ユースケース別:NotionとConfluenceの適材適所
以上の比較を踏まえて、組織のタイプや文化によってどちらのツールがより適しているかを具体的なユースケース別に考えてみましょう。エンジニア中心の組織か否か、ドキュメント文化の成熟度合い、組織規模などによって、NotionとConfluenceの向き不向きは変わり得ます。
エンジニア組織 vs 非エンジニア組織
ソフトウェアエンジニアや開発部門が主な利用者となる場合、Confluenceが選ばれるケースが多く見られます。その理由の一つは、ConfluenceがJira(課題管理)やBitbucket(コード管理)など開発プロセスの中核ツールと密接に連携でき、開発ワークフローの延長線上でドキュメント管理を行えることです。例えば開発プロジェクトの要件や設計書をConfluenceで管理し、関連するJiraチケットと相互参照することで、仕様と実装タスクを行き来しやすくなります。またConfluenceは技術ドキュメント(API仕様書、アーキテクチャ設計など)の管理に長けており、コードブロックやバージョン管理、変更履歴のハイライト表示などエンジニアに嬉しい機能が揃っています。そのため開発組織にはConfluenceというのが定番の組み合わせになっています。
一方で人事・総務・営業・マーケティングなど非エンジニア部門や、小規模プロジェクトチームにはNotionがフィットしやすい傾向があります。Notionはドキュメントだけでなくタスクボードやデータベースも統合されているため、たとえばマーケティングチームがコンテンツカレンダーを管理しつつ、そのまま各コンテンツのガイド文書も記載する、といった一元管理が可能です。またUIが洗練されており抵抗感が少ないため、ITリテラシーが高くないメンバーでも直感的に操作できます。エンジニア以外の部門では往々にして「ツールが複雑だと使われない」問題がありますが、Notionであれば社内SNS感覚で情報を書き込めるため導入ハードルが低いと言えます。さらにNotionはノートテイキングやブレインストームのホワイトボード代わりとしても使える柔軟さがあり、クリエイティブな職種のアイデア出しからバックオフィスの手順書まで幅広くカバーできる点も評価されています。総じて非エンジニア組織にはNotionが親和性高く、まず情報を集約するプラットフォームとして受け入れられやすいでしょう。
もちろん最近ではエンジニア組織でNotionを使う例や、非エンジニア部門でConfluenceを使う例もあります。例えばスタートアップ企業ではエンジニアも含め全社でNotionを採用し、ドキュメントとタスク管理を一本化しているケースがあります(Confluence+Jiraの組み合わせをNotion一つで代替するイメージ)。逆に保守的な大企業では情シス主導で全社的にConfluenceを導入し、技術部門以外もConfluenceで議事録や手順書をまとめる運用も見られます。このように部門の性質だけで決まるものではありませんが、一般論として自社の主要業務ツールとの親和性やメンバーのITスキル水準を考慮すると選びやすくなります。
ドキュメント文化の成熟度・運用体制の違い
次に、組織内のドキュメント文化や情報管理の運用体制という観点で適性を考えてみます。
ドキュメント文化が未成熟で、「これから社内ナレッジを整備していきたい」という段階の組織には、Notionのような簡単にページを作成・編集できるツールが適しています。社内Wikiを導入してもページ作成や編集が難しいと結局活用が進まないため、どんなユーザーでも直感的に扱えるNotionであればまず情報蓄積の第一歩を踏み出しやすいでしょ。実際、多くの企業で課題となっている「ナレッジが散逸して活用されていない」という問題に対し、まずは社員が気軽にメモや手順書を残せる環境を整えることが重要です。Notionはそのハードルを下げるツールとして有効であり、「まず書いてもらう」文化づくりに貢献します。さらにNotionにはコメント機能などもあり、カジュアルにナレッジ収集・コミュニケーションを活性化させやすい雰囲気があります。形式張らずにどんどん情報を書き留めるにはNotionの方が心理的障壁が低いという声も多いです。
逆に既にドキュメント文化が根付いており、情報の体系化や品質維持に重きを置く組織ではConfluenceが力を発揮します。社内で文書管理のルールや分類法が確立している場合、Confluenceの構造化されたスペースとページ階層はその運用に適しています。例えばISO準拠の品質マニュアルや開発標準をナレッジベース化する際、Confluenceなら改訂履歴の管理や承認フロー(アドオン利用)、体系的な目次作成などが容易です。Notionでも運用次第で可能ですが、Confluenceは始めから「公式文書を扱う場」としての印象があるため、社員にも「ここに蓄積された情報は正式なナレッジだ」という認識を与えやすい利点があります。また情報量が膨大になってきた場合でも、前述のとおりConfluenceは検索やラベル機能で必要な知識を掘り起こしやすいため、ナレッジ資産を埋もれさせず長期的に管理するのに適しています。既にWiki文化がある程度成熟しているなら、Confluenceの方が社内ルールに沿った厳密な運用が可能で安心感があるでしょう。
まとめると、「まずは書く文化を醸成したい」段階ではNotion、 「蓄積されたナレッジを体系立てて管理したい」段階ではConfluenceが向いていると言えます。ただしNotionも前述のページオーナー機能などでコンテンツ品質管理を支援するなどエンタープライズ向け機能が進化していますし、Confluenceも新機能としてホワイトボードやデータベース要素を取り入れるなど柔軟性を高めています。ツール側の進化によって理想的な運用に近づけることも可能になってきています。
両ツールを併用するケースと棲み分け
組織によってはNotionとConfluenceの両方を併用しているケースもあります。これはややレアケースではありますが、例えば部門ごとに好みのツールが異なる場合や、用途によって使い分けたい場合に発生します。併用時には情報が分散しやすいため注意も必要ですが、上手に棲み分けることで互いの長所を享受することも可能です。
併用事例と想定シナリオ
現実の併用例としては、開発部門はConfluence、非開発部門はNotionといったように部署単位でツールを分けているケースがあります。この場合、例えばエンジニアが参照すべき技術設計や仕様はConfluenceに蓄積し、一方で会社全体の人事ポリシーや営業ナレッジはNotion上にまとめる、といった使い分けになります。それぞれの部署が使いやすいツールを採用することで部門内の生産性は高まりますが、組織横断の情報共有には工夫が必要です。また、移行期間中の一時的な併用も見られます。従来Confluenceを使っていたがNotionに移行を検討している、といった場合に、しばらく両方に情報が併存することがあります。このような時期には、新規の情報はNotionに集約しつつ、過去のConfluence資産も参照できるようリンクを貼るなどしてメンバーが混乱しないよう配慮することが重要です。
併用のもう一つのシナリオとしては、用途によるハイブリッド運用があります。例えば、「正式なプロジェクト文書はConfluenceで管理するが、日々の議事メモやタスク出しはNotionで行い、完成した文書だけConfluenceにアーカイブする」という方法です。Notionのスピード感を活かして下書きやコラボレーションを行い、最終成果物はConfluenceのナレッジベースに残すことで、両方のメリットを得る形です。この運用では二重管理にならないよう明確なルール決めが不可欠ですが、社内Wiki担当者からは「みんなが書きやすいNotionでまず書かせて、後で整った形でConfluenceに掲載する」というアプローチは実務的との声もあります。
併用時の棲み分けと統合のポイント
NotionとConfluenceを併用する際には、以下のポイントに留意すると良いでしょう。
- 利用範囲を明確化する: どの情報をどちらのツールに蓄積するかをルール化します(例:「技術ドキュメントはConfluence、社内手順マニュアルはNotion」など)。誰がどちらを見れば必要な情報にアクセスできるか、社内に周知することが大切です。
- 重複登録を避ける: 同じ内容を両方に書くことは極力避け、一方から他方へのリンクを貼るなどして単一の情報源を保ちます。例えばNotionのページから関連するConfluenceページへのリンク集を用意し、行き来しやすくする工夫が考えられます。
- 自動連携ツールの活用: 最近では、NotionとConfluence間でデータを同期するツールやスクリプトも登場しています。例えば、Notionのデータベースに新しい項目を追加したら自動でConfluenceにページを生成するといった連携が可能なソリューションがあります。こうした自動化を使えば手作業による二重管理を減らし、併用による手間を軽減できます。
- 統一検索の仕組み: 理想的には両方の情報を一括検索できる環境が望ましいです。社内ポータル等にGoogleカスタム検索を導入して両リポジトリを横断検索する仕組みを作ったり、Zapier連携でNotionページの更新通知をConfluence側に記録する等、情報の所在を横断的に把握できる工夫も検討しましょう。
併用は運用コストが上がるため可能ならどちらかに集約することが望ましいですが、どうしても両方の強みを使いたい場合は上記のような対策で「棲み分けと連携」を図ることがポイントです。何より組織内の合意形成とメンバーへの周知徹底が重要になります。
おわりに:組織の目的に応じた最適な選択を
ここまで見てきたように、NotionとConfluenceはいずれも優れたナレッジ管理ツールであり、それぞれが異なる強みを持っています。一方が他方の完全上位互換というわけではなく、組織の規模・目的・文化によって向き不向きが分かれる「使い分ける価値のあるツール同士」です。選定にあたって重要なのは、自社の課題や目的を明確にした上で、それに合致する方を選ぶことです。例えば「部署を越えて統制のとれた情報共有基盤を構築したい」のであればConfluenceが有力候補になるでしょうし、「プロジェクト運営に必要な機能を一体で使えてメンバーが抵抗なく使えるツールが欲しい」ならNotionが適しているかもしれません。
幸いなことに両ツールとも無料プランやトライアルが提供されており、実際に試しながら比較検討することも可能です。また、本記事で触れたようなエンタープライズ機能や移行方法について更に詳しく知りたい方、組織に合ったナレッジツール選びに悩まれている方はぜひお気軽にご相談ください。当社はNotion及びConfluence双方の正規販売パートナーとして、お客様の要件に応じた最適な導入プランをご提案いたします。それぞれの強みを正しく理解し、自社の目的に応じたツール選択でナレッジマネジメントを強化しましょう。お問い合わせをお待ちしております。