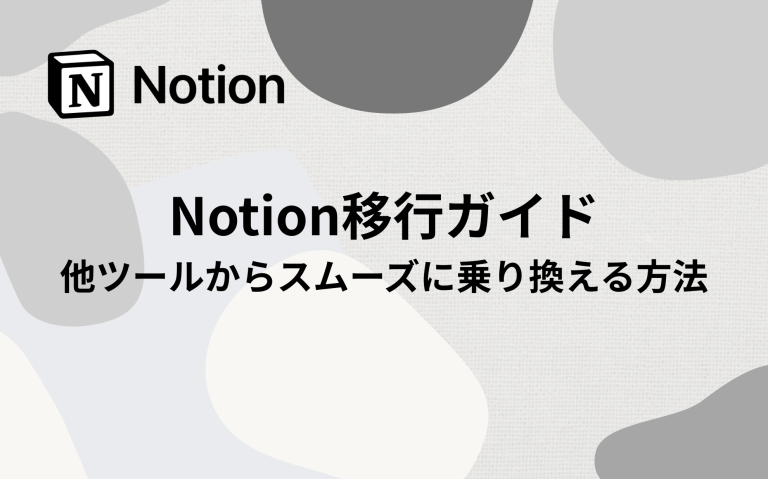е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҜеў—гҒҲгӮӢгҒ®гҒ«гҖҒгӮігӮ№гғҲгӮӮеў—гӮ„гҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҫгҒҷгҒӢпјҹвҖ•вҖ•JSMгҒ§вҖңгғ гғҖгҒӘйҒӢз”ЁгӮігӮ№гғҲвҖқгӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒҷгӮӢж–№жі•

- еҹ·зӯҶиҖ…
-
 asleadз·ЁйӣҶйғЁ
asleadз·ЁйӣҶйғЁгҒ“гӮ“гҒ«гҒЎгҒҜгҖӮasleadз·ЁйӣҶйғЁгҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖж–°гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўй–ӢзҷәгҒ®гғҲгғ¬гғігғүгҒӢгӮүгҖҒAIгғ»DXгғ„гғјгғ«гҒ®еҠ№жһңзҡ„гҒӘжҙ»з”Ёжі•гҖҒдјҒжҘӯгҒ®ITгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®еј·еҢ–гҖҒжҘӯеӢҷеҠ№зҺҮеҢ–гӮ„DXеҢ–гӮ’жҲҗеҠҹгҒ«е°ҺгҒҸгӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігҒҫгҒ§гҖҒе№…еәғгҒ„иЁҳдәӢгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дјҒжҘӯгҒҢзӣҙйқўгҒҷгӮӢиӘІйЎҢгҒ®и§Јжұәзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘгғ„гғјгғ«гҒ®жҙ»з”Ёж–№жі•гӮ’жҺўжұӮгҒ—гҖҒз”ҹз”ЈжҖ§гҒ®еҗ‘дёҠгҒ«з№ӢгҒҢгӮӢе®ҹи·өзҡ„гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠеұҠгҒ‘гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ йғЁй–ҖгҒ®гғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒ®зҡҶж§ҳгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣз®ЎзҗҶгғ„гғјгғ«гҒ®гӮігӮ№гғҲгҒ«гҒҠжӮ©гҒҝгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮеҲ©з”ЁйғЁй–ҖгӮ„е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒҹгҒігҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒ«жҜ”дҫӢгҒ—гҒҰгғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№иІ»з”ЁгӮӮйқ’еӨ©дә•гҒ«иҶЁгӮүгӮ“гҒ§гҒ„гҒҸвҖ•вҖ•гҒқгӮ“гҒӘзҸҫзҠ¶гҒ«з–‘е•ҸгӮ’ж„ҹгҒҳе§ӢгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢж–№гӮӮеӨҡгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮжң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣз®ЎзҗҶгҒ«жҪңгӮҖвҖңгғ гғҖгҒӘйҒӢз”ЁгӮігӮ№гғҲвҖқгҒ®жӯЈдҪ“гҒЁгҖҒJira Service ManagementпјҲд»ҘдёӢгҖҒJSMпјүгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҒқгҒ®гӮігӮ№гғҲж§ӢйҖ гӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒҷгӮӢж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
1. гҒӘгҒңе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣз®ЎзҗҶгҒҜвҖң無駄гҒӘгӮігӮ№гғҲвҖқгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гҒӢпјҹ
еӨҡгҒҸгҒ®е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣз®ЎзҗҶгғ„гғјгғ«гҒҜгҖҒгҖҢгғҰгғјгӮ¶гғјж•°иӘІйҮ‘гҖҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’гҒҷгӮӢеҫ“жҘӯе“ЎгӮ„йЎ§е®ўгҖҒе…Ёе“ЎеҲҶгҒ®гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№иІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮITйғЁй–ҖгҒ®гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢж•°еҗҚгҒ§гӮӮгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’дҪҝгҒҶгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢж•°зҷҫдәәиҰҸжЁЎгҒӘгӮүгҖҒе…Ёе“ЎеҲҶгҒ«жҜҺжңҲгӮігӮ№гғҲгҒҢзҷәз”ҹгҖӮе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢеў—гҒҲз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ»гҒ©гҖҒиІ»з”ЁгӮӮйқ’еӨ©дә•гҒ§еў—гҒҲз¶ҡгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгҖҢгғҰгғјгӮ¶гғјж•°пјқгӮігӮ№гғҲеў—гҖҚгҒ®д»•зө„гҒҝгҒ§гҒҜгҖҒдҪҝгӮҸгҒӘгҒ„гғҰгғјгӮ¶гғјгӮ„еҲ©з”Ёй »еәҰгҒ®дҪҺгҒ„гӮўгӮ«гӮҰгғігғҲгҒ«гӮӮиІ»з”ЁгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҖҒ無駄гҒӘж”ҜеҮәгҒҢиҶЁгӮүгӮҖдёҖж–№гҒ§гҒҷгҖӮе№ҙеәҰжӣҙж–°гҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҖҒжғіе®ҡд»ҘдёҠгҒ®гӮігӮ№гғҲгҒ«й©ҡгҒӢгҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҒӮгӮӢдјҒжҘӯгҒ§гҒҜеҫ“жқҘгғ„гғјгғ«еҲ©з”ЁжҷӮгҒ«гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№иІ»з”ЁгҒҢ10дёҮгғүгғ«д»ҘдёҠгҒ«йҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒJSMгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҰ100еҗҚгҒ®гӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲдҪ“еҲ¶гҒ«гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№иІ»з”ЁгӮ’60%ең§зё®гҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶе ұе‘ҠгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ®дәәгҖҚгҒҫгҒ§е…Ёе“ЎиӘІйҮ‘вҖ•вҖ•гҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒ“гҒқгҒҢгҖҒ無駄гҒӘгӮігӮ№гғҲгҒ®жё©еәҠгҒ§гҒҷгҖӮ
2. дҫЎж јгҒҢиҶЁгӮүгӮҖж§ӢйҖ гӮ’ж №жң¬гҒӢгӮүеӨүгҒҲгӮӢгҖҒJSMгҒ®д»•зө„гҒҝ
гҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгҖҢгғҰгғјгӮ¶гғјж•°гҒ«еҝңгҒҳгҒҰйҡӣйҷҗгҒӘгҒҸгӮігӮ№гғҲгҒҢиҶЁгӮүгӮҖгҖҚж§ӢйҖ гӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӨүгҒҲгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒқгҒ®зӯ”гҒҲгҒҢJira Service Management (JSM) гҒ®жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲиӘІйҮ‘гғўгғҮгғ«гҒ§гҒҷгҖӮJSMгҒ§гҒҜгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣеҜҫеҝңгӮ’иЎҢгҒҶгҖҢгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲгҖҚгҒ®дәәж•°гҒ гҒ‘гҒ«гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№гӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮҢгҒ°OKгҒ§гҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’иЎҢгҒҶеҒҙгҒ®гғҰгғјгӮ¶гғјпјҲгӮ«гӮ№гӮҝгғһгғјпјүгҒҜдҪ•дәәиҝҪеҠ гҒ—гҒҰгӮӮгғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№гҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮиЁҖгҒ„жҸӣгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгӮігӮ№гғҲгҒ®иЁҲз®—еҹәжә–гҒҢгҖҢеҜҫеҝңгҒҷгӮӢдәәгҒ®ж•°гҖҚгҒ гҒ‘гҒ«зөһгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғјпјҲдҫқй јиҖ…пјүгҒ®ж•°гҒҜз„ЎеҲ¶йҷҗгҒ§гӮӮиҝҪеҠ иІ»з”ЁгҒҜзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®д»•зө„гҒҝгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзө„з№”еҶ…гҒ§гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢеў—гҒҲгҒҰгӮӮгӮігӮ№гғҲгҒҢйқ’еӨ©дә•гҒ«и·ігҒӯдёҠгҒҢгӮӢеҝғй…ҚгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒзңҹгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘйғЁеҲҶгҒ«гҒ гҒ‘жҠ•иіҮгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘еў—гҒҲгҒҰгӮӮгҖҒеҜҫеҝңгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲж•°гҒҢеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гӮігӮ№гғҲгҒҜеў—гҒҲгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒзө„з№”гҒ®жҲҗй•·гӮ„еҲ©з”ЁйғЁй–ҖгҒ®жӢЎеӨ§гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰжҹ”и»ҹгҒ«гӮөгғјгғ“гӮ№гғҮгӮ№гӮҜгӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°ж–°гҒҹгҒ«йғЁзҪІгӮ„гғҒгғјгғ гҒҢгӮөгғјгғ“гӮ№гғҮгӮ№гӮҜгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—е§ӢгӮҒгҒҰгӮӮгҖҒгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲгҒ®еў—е“ЎгҒҢдёҚиҰҒгҒӘйҷҗгӮҠгғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№иҝҪеҠ гҒ®гӮігӮ№гғҲгҒҜгӮјгғӯгҖӮзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢеҝ…иҰҒд»ҘдёҠгҒ«ж”Ҝжү•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹйғЁеҲҶгҖҚгӮ’ж №жң¬гҒӢгӮүеүҠжёӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«JSMгҒ§гҒҜгҖҒгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲиӘІйҮ‘гғўгғҮгғ«гҒ«гӮҲгӮӢгӮігӮ№гғҲжңҖйҒ©еҢ–гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣеҜҫеҝңгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢиұҠеҜҢгҒӘж©ҹиғҪгӮӮеӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮITILжә–жӢ гҒ®гӮӨгғігӮ·гғҮгғігғҲз®ЎзҗҶгғ»гӮөгғјгғ“гӮ№гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲз®ЎзҗҶгғ»еӨүжӣҙз®ЎзҗҶгғ»е•ҸйЎҢз®ЎзҗҶгҒӘгҒ©гҒҢзөұеҗҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒWebгғқгғјгӮҝгғ«гӮ„гғЎгғјгғ«гҖҒгғҒгғЈгғғгғҲгҒӘгҒ©иӨҮж•°гғҒгғЈгғҚгғ«гҒӢгӮүгҒ®е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’дёҖе…ғз®ЎзҗҶгҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝгҒҢж•ҙгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲгҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’й§ҶдҪҝгҒ—гҒҰеҠ№зҺҮгӮҲгҒҸеҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе°‘дәәж•°гҒ®еҜҫеҝңгғҒгғјгғ гҒ§гӮӮеӨҡж•°гҒ®е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’гҒ•гҒ°гҒ‘гӮӢгҒ®гӮӮгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢгғҰгғјгӮ¶гғјз„ЎеҲ¶йҷҗгҒ§гӮӮгӮігӮ№гғҲеў—гҒӘгҒ—гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдҫЎж јгғўгғҮгғ«гҒЁгҖҒе……е®ҹгҒ—гҒҹж©ҹиғҪгҒ«гӮҲгӮӢй«ҳеҠ№зҺҮгҒӘеҜҫеҝңвҖ”вҖ”JSMгҒҜгҒ“гҒ®дәҢи»ёгҒ§гҖҒ無駄гҒӘйҒӢз”ЁгӮігӮ№гғҲгҒ®еүҠжёӣгҒЁгӮөгғјгғ“гӮ№е“ҒиіӘеҗ‘дёҠгҒ®дёЎз«ӢгӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
3. JSMгҒ®ж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҒЈгҒЁзҹҘгӮҠгҒҹгҒ„ж–№гҒё
JSMгҒҢеҫ“жқҘгҒ®е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣз®ЎзҗҶгғ„гғјгғ«гҒЁз•°гҒӘгӮӢдҫЎж јгғўгғҮгғ«гӮ’е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢиғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒдёҠиҝ°гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«ITгӮөгғјгғ“гӮ№гғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲпјҲITSMпјүгғ„гғјгғ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®з·ҸеҗҲеҠӣгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғҠгғ¬гғғгӮёгғҷгғјгӮ№гҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒ«гӮҲгӮӢгӮ»гғ«гғ•гғҳгғ«гғ—дҝғйҖІгӮ„гҖҒSLAз®ЎзҗҶгҒ«гӮҲгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№ж°ҙжә–гҒ®з¶ӯжҢҒгҖҒиҮӘеӢ•еҢ–гғ«гғјгғ«гҒ«гӮҲгӮӢжүӢдҪңжҘӯгҒ®еүҠжёӣгҒӘгҒ©гҖҒJSMгҒ«гҒҜзҸҫе ҙгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢеӨҡеҪ©гҒӘж©ҹиғҪгҒҢжҸғгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹж©ҹиғҪгҒ®и©ізҙ°гӮ„жҙ»з”Ёж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҲҲе‘ігӮ’гҒҠжҢҒгҒЎгҒ®ж–№гҒҜгҖҒгҒңгҒІд»ҘдёӢгҒ®иЁҳдәӢгӮӮеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
- Jira Service Managementеҫ№еә•гӮ¬гӮӨгғүпјҡ ITгӮөгғјгғ“гӮ№з®ЎзҗҶгӮ’еӨүйқ©гҒҷгӮӢ4гҒӨгҒ®еҹәжң¬ж©ҹиғҪгҒЁгғҷгӮ№гғҲгғ—гғ©гӮҜгғҶгӮЈгӮ№
- Jira Service ManagementгҒ§жҘӯеӢҷгӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒҷгӮӢ4гҒӨгҒ®иЁӯе®ҡгғқгӮӨгғігғҲ
- Jira Service ManagementгҒ§е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гғҮгӮ№гӮҜйҒӢз”ЁпјҡеҲқеҝғиҖ…еҗ‘гҒ‘гӮ¬гӮӨгғү
дёҠиЁҳгҒ®гғӘгғігӮҜе…ҲгҒ§гҒҜгҖҒJSMгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘж©ҹиғҪи§ЈиӘ¬гӮ„е°Һе…ҘгғЎгғӘгғғгғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ•гӮүгҒ«ж·ұгҒҸзҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдҫЎж јйқўгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҖҢе®ҹйҡӣгҒ«гҒ©гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒӢпјҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гҒӢгӮүгӮӮJSMгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒиҮӘзӨҫгҒ®иӘІйЎҢи§ЈжұәгҒ«гҒҠеҪ№з«ӢгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
4. е°Һе…ҘгӮ’иҝ·гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒёпјҡдҫЎж јж§ӢйҖ гӮ»гғ«гғ•гғҒгӮ§гғғгӮҜ
JSMгҒёгҒ®еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгӮ„ж–°иҰҸе°Һе…ҘгҒ«иҲҲе‘ігҒҜгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгҖҢжң¬еҪ“гҒ«гҒҶгҒЎгҒ§еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҚгҒЁгҒҠжӮ©гҒҝгҒ®ж–№гҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҒ®иҮӘзӨҫзҠ¶жіҒгӮ’гӮ»гғ«гғ•гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮд»ҘдёӢгҒ®иіӘе•ҸгҒ«зӯ”гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒд»ҠгҒ®е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣз®ЎзҗҶгғ„гғјгғ«гҒ®гӮігӮ№гғҲж§ӢйҖ гҒ«з„Ўй§„гҒҢжҪңгӮ“гҒ§гҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮ’зӮ№жӨңгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
- е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғјж•°гҒҜгҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„еў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢпјҹ зҸҫеңЁгҖҒзӨҫеҶ…еӨ–гҒ§е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’иЎҢгҒҶгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҜдҪ•дәәгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®ж•°гҒҜжҳЁе№ҙгҒӢгӮүеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹд»ҠеҫҢгҒ•гӮүгҒ«йғЁй–ҖжӢЎеӨ§гӮ„гғҰгғјгӮ¶гғјеў—еҠ гҒ®иҰӢиҫјгҒҝгҒҜгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
- гӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰе®ҹйҡӣгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜдҪ•дәәпјҹ е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣеҜҫеҝңгҒ®е°Ӯд»»жӢ…еҪ“иҖ…пјҲгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲпјүгҒҜдҪ•дәәгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгҒ®дәәж•°гҒҜе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғјж•°гҒ«жҜ”гҒ№гҒҰгҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒ®иҰҸжЁЎгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҲдҫӢпјҡгғҰгғјгӮ¶гғј100дәәгҒ«еҜҫгҒ—еҜҫеҝңиҖ…5дәәгҒӘгҒ©пјүгҖӮ
- гӮӮгҒ—е…Ёе“ЎгҒ«гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№ж–ҷгҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҒ„гҒҸгӮүжү•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјҹ зҸҫеңЁеҲ©з”ЁдёӯгҒ®гғ„гғјгғ«гҒ§е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғје…Ёе“ЎеҲҶгҒ®гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№иІ»з”ЁгӮ’иЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒе№ҙй–“гҒҫгҒҹгҒҜжңҲй–“гҒ§гҒ©гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®йҮ‘йЎҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹгҒқгҒ®гӮігӮ№гғҲгҒҜгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲгҒ®дәәж•°иҰҸжЁЎгҒӢгӮүиҰӢгҒҰйҒ©еҲҮгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®е•ҸгҒ„гҒ«з…§гӮүгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҖҒгҖҢеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®ж•°гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮігӮ№гғҲгҒҢиҰӢеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҖҚгҖҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’гҒ—гҒӘгҒ„дәәгҒ«гӮӮиІ»з”ЁгӮ’жү•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«д»ҠгҒҢгӮігӮ№гғҲж§ӢйҖ гӮ’иҰӢзӣҙгҒҷгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҒҷгҖӮJSMгҒӘгӮүгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«еҜҫеҝңгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲеҲҶгҒ®гӮігӮ№гғҲгҒ гҒ‘гҒ«йӣҶдёӯгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢеў—гҒҲгҒҰгӮӮ無駄гҒӘеҮәиІ»гӮ’жҠ‘гҒҲгҒӨгҒӨгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣгӮ’жӢЎеӨ§еҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮзҸҫеңЁгҒҠдҪҝгҒ„гҒ®гғ„гғјгғ«гҒ®еҘ‘зҙ„жӣҙж–°гӮ„д»–иЈҪе“ҒгҒёгҒ®гғӘгғ—гғ¬гӮӨгӮ№гӮ’жӨңиЁҺдёӯгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒңгҒІдёҖеәҰJSMгҒ®гӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲиӘІйҮ‘гғўгғҮгғ«гҒ«гӮҲгӮӢеҠ№жһңгӮ’и©Ұз®—гҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒJSMгҒ®е°Һе…ҘгӮ„ж–ҷйҮ‘гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®гҒ”зӣёи«Үгғ»гҒҠиҰӢз©ҚгӮҠгҒҜгҖҒasleadгҒ§жүҝгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢгғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№иІ»з”ЁгӮ’гӮӮгҒЈгҒЁеҗҲзҗҶзҡ„гҒ«жҠ‘гҒҲгҒҹгҒ„гҖҚгҖҢе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒ©гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гӮігӮ№гғҲеүҠжёӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢзҹҘгӮҠгҒҹгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮӮеӨ§жӯ“иҝҺгҒ§гҒҷгҖӮгҒҠж°—и»ҪгҒ«asleadгҒёгҒ®гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢиІҙзӨҫгҒ®иӘІйЎҢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒжңҖйҒ©гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гғҮгӮ№гӮҜз’°еўғгҒ®е®ҹзҸҫгӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ