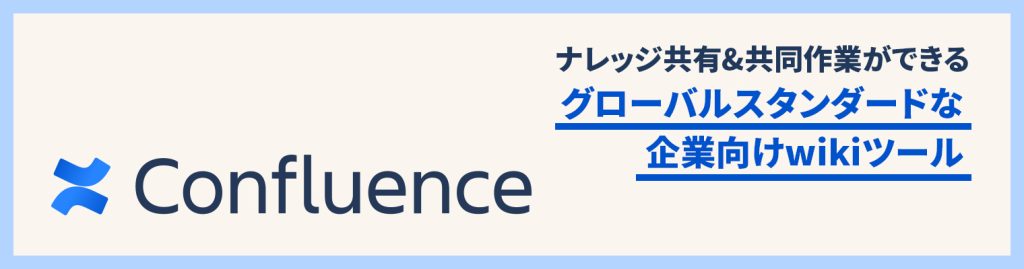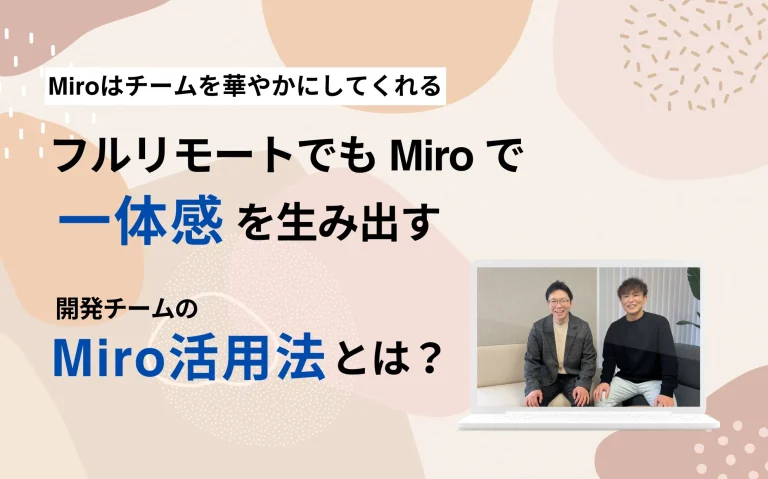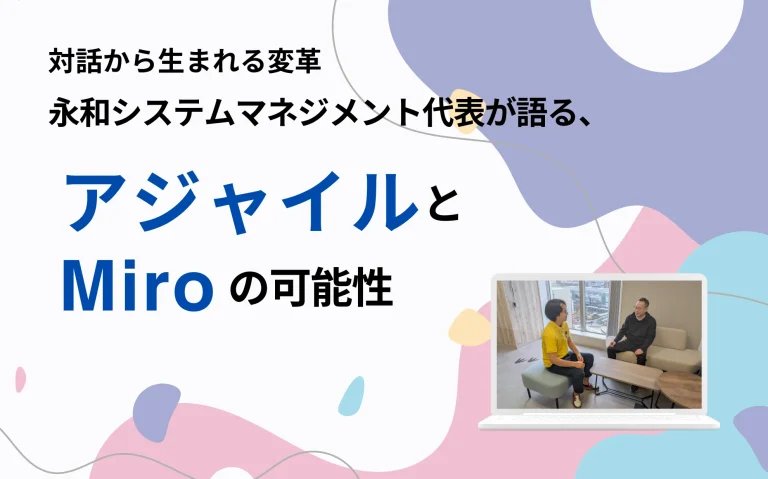ConfluenceとoViceで実現する、リモートワーク時代の新しい働き方

- 執筆者
-
 aslead編集部
aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。
最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。
企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。
こんにちは、aslead マーケティング担当の金山です。
永和システムマネジメント インタビューツアーの第2弾です。
今回お話を聞くのは、永和システムマネジメントの山口さんと見澤さんのお二人です。
お二人は北國銀行が進めているインターネットバンキング開発プロジェクトに参画しています。今回はそんなプロジェクトチームでの働き方とSaaS製品の使い方の工夫をお聞きしました。
永和システムマネジメント 山口さん:北國銀行の個人向けインターネットバンキングの開発に携わっています。基本的には開発者でバックエンドをやっています。この会社では8年ほど働いています。
永和システムマネジメント 見澤さん:北國銀行の個人向けインターネットバンキングの開発で主にバックエンド開発を担当しています。プロジェクト加入2年目で、覚えることが多くて大変ですが、日々勉強中です。
永和システムマネジメント のどぐろチームの山口さん(左)と見澤さん(右)

具体的な仕事の内容を詳しく教えてください
クラウドに向けたAPIの開発や、マイクロサービスの構築を行っています。 インフラは専門のチームが担当しています。
具体的には、品質向上に向けた取り組みの中で、APIを使ったマイクロサービスを構築し、それぞれを連携させてシステム全体を構成しています。 データの保存や処理なども、マイクロサービス単位で管理しています。
API周りのバックエンド開発だけでなく、一部ではありますが、開発環境や本番環境のインフラ設定などにも携わっています。
アジャイル開発のサイクルやリモートワークでのコミュニケーション方法について教えてください
スクラム開発を採用し、2週間を1スプリントとして開発を進めています。 リモートワークが中心で、バーチャルオフィスツール「oVice」に毎日「出社」しています。
朝会はoViceのバーチャルオフィスに集まって行います。 チームメンバーは、それぞれ決まった場所にアバターを配置しています。
oViceは常時接続していますが、マイクとカメラはオフにしています。 話したいときは、マイクをオンにして話しかける、まるで実際のオフィスにいるような感覚です。
oViceを利用して出社している様子を説明する見澤さん

チームでの情報共有をスムーズにするための工夫を教えてください
コミュニケーションには、oVice、Mattermost、Miroなどを使っています。 ドキュメント管理には、Confluenceを利用しています。 ソースコードの管理にはAzure DevOpsも使っています。
Confluenceには、設計書、議事録、個人メモなど、あらゆる情報を集約しています。
議事録は、Confluenceのページにみんなで書き込んでいきます。
SaaS間の連携で言うと、Confluenceのコメントでメンションすると、Mattermostに通知が飛ぶように設定しています。
チーム全体で情報共有を促進するために、分かったことはなるべくConfluenceに残すようにし、関連ページを整理することで、必要な情報にすぐにアクセスできるようにしています。
導入による変化や効果を教えてください
oViceは、バーチャルオフィスのような感覚で、気軽に話しかけられるので、コミュニケーションが活発になりました。 Confluenceも、情報共有がスムーズになり、チーム全体で知識を共有できるようになりました。
Confluenceにあらゆる情報を集約することで、チームメンバー全員が、いつでも必要な情報にアクセスできるようになりました。 特に、新人にとっては、過去の記録やナレッジを参考にできるのは、とても助かります。
Confluence導入の経緯と導入後の効果はなんですか?
私たちのチームでは、プロジェクトの進行に伴い、ドキュメント管理の課題に直面していました。ドキュメントはSharePointやGitのリポジトリなどに散在しており、必要な情報を探し出すのに多くの時間を費やしていました。特に設計ドキュメントを作成する際には、PlantUMLやdraw.ioなど複数のツールを使いこなす必要があり、さらにマークダウン記法の習熟も求められるため、これが新しいメンバーにとっての参画障壁となっていました。
このような状況を改善するために、開発チームではConfluenceの導入を決定しました。Confluenceはドキュメントを一元管理できるだけでなく、豊富なマクロ機能を持ち、さまざまなツールとの連携が可能である点が魅力でした。
Confluenceを導入した結果、ドキュメント管理の効率が飛躍的に向上しました。まず、ドキュメントがConfluenceに集約されたことで、設計書やナレッジの検索が迅速になり、必要な情報にすぐにアクセスできるようになりました。これにより、プロジェクトの進行がスムーズになり、チーム全体の生産性が向上しました。
さらに、Confluenceの豊富なマクロ機能を活用することで、PlantUMLやdraw.ioなどの外部ツールを使わずにConfluence内でリッチなドキュメントを作成できるようになりました。これにより、ドキュメント作成の手間が大幅に軽減され、より多くの時間を本来の業務に充てることができるようになりました。
また、ConfluenceのAPIを活用することで、プロジェクトで作成した各種ツールとの連携が可能となり、Gitで管理しているソースコードからドキュメントを自動生成できるようになりました。これにより、ドキュメントの更新が自動化され、常に最新の情報を維持できるようになりました。
さらに、プロジェクトで独自に開発したマクロを使用することで、開発環境のデプロイ状況の可視化や、AIによるドキュメントの自動レビューといった機能も実装でき、プロジェクトの品質向上にも貢献しています。
AIも絡めたConfluenceの活用例
生成AIの進化は、ドキュメント管理にも大きな変化をもたらしています。
Confluenceにも生成AIを活用した機能が多数搭載されていますが、私たちのドキュメント管理には、さらに特化した機能が必要でした。
そこで、拡張プラグインとして「AIによるレビュー機能」を開発し、ドキュメントの品質向上を図れないか検討を進めています。Confluenceは柔軟性が高く、非常に使い勝手が良いと感じています。
まとめ
本日は、永和システムマネジメントのお二人にお話を伺いました。北國銀行のインターネットバンキングの開発において、Confluenceがどのように活用されているのか、その具体的な方法や効果について詳しく知ることができました。
フルリモートでの開発において、Confluenceは単なるドキュメント管理ツールではなく、チームのナレッジを共有し、コミュニケーションを活性化することで、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献していることがわかりました。
特に、議事録をConfluence上で作成することで、情報共有をスムーズにし、チームメンバー全員が、いつでも必要な情報にアクセスできるようにしている点は、大変興味深いお話でした。
今後も、Confluenceが進化し、より多くのチームで活用されることで、より良いコミュニケーションが促進され、創造的なアイデアが生まれることを期待しています。
asleadではConfluenceを始めとしたアトラシアンツールの代理店をしております。今回のインタビューをきっかけにConfluenceに興味を持たれた方は下記よりお問い合わせください