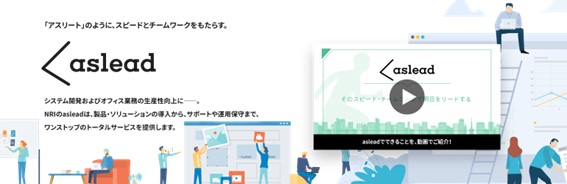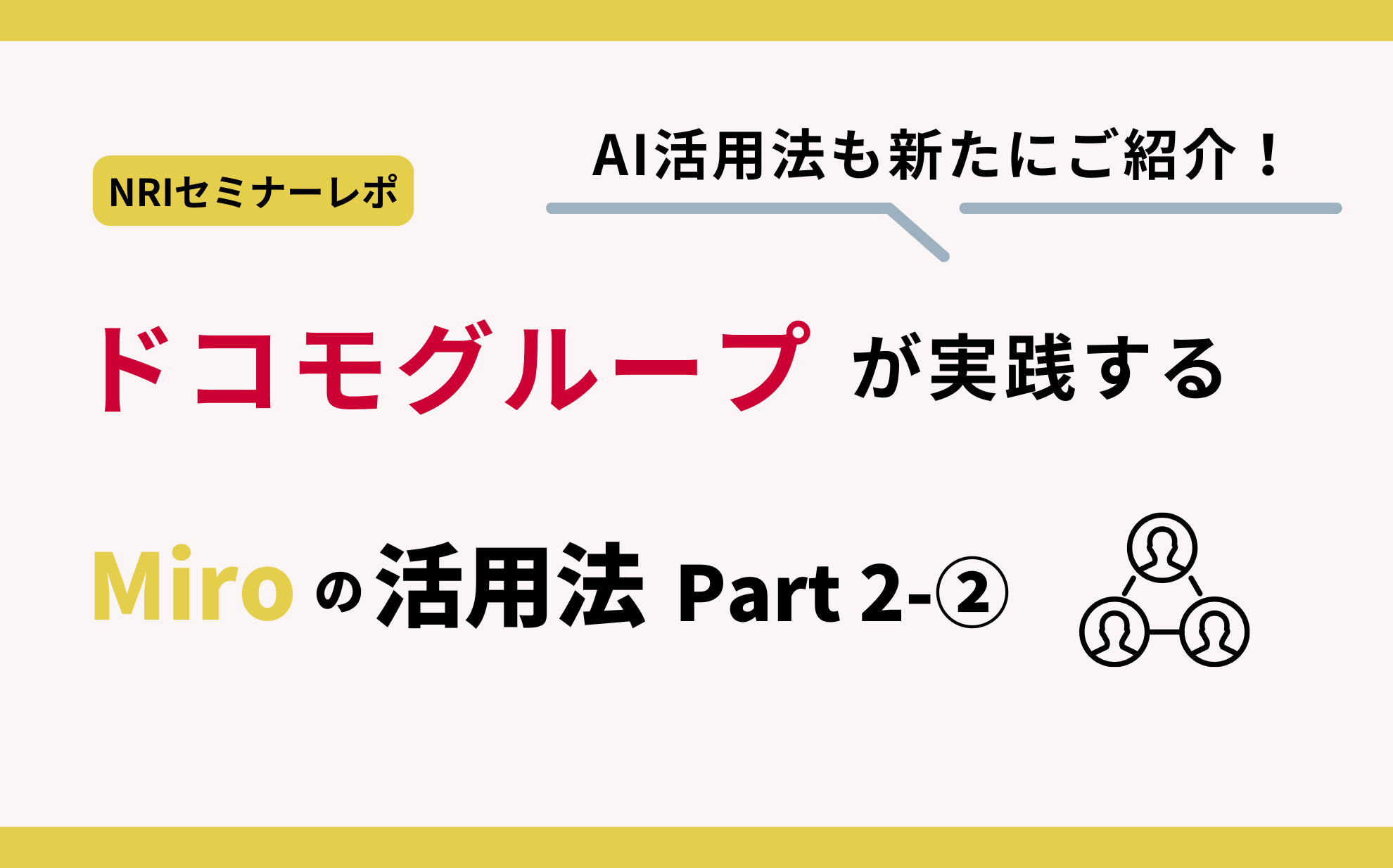生産性向上の目的とは?具体的な取り組み方、企業にもたらすメリットを解説

- 執筆者
-
 aslead編集部
aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。
最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。
企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。
持続的な経営を目指す上で、生産性向上は避けて通れない課題です。
技術革新の活用、業務プロセスの効率化、従業員のスキルアップなど、さまざまな側面から生産性向上を追求することで、企業はその競争力を強化し、持続可能な成長を実現することができます。
しかし、「生産性向上ってどういう意味?」「具体的に何をすればいいの?」など、その意味や取り組むべき具体的な方法については、すぐには浮かばないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、生産性向上の目的や具体的な取り組み方、企業にもたらすメリットについてわかりやすく解説します。
そもそも生産性とは?

生産性とは、投入された資源に対してどのくらいの成果を生み出したのか、その比率をあらわすものです。
限られた資源を最大限に活用し、効率的かつ効果的に業務を遂行することが、生産性向上につながります。
生産性向上について知る前に、まずはその前提知識として、ビジネスにおける生産性の意味、生産性の比率を求める計算式について理解していきましょう。
生産性の意味・定義
ビジネスの世界でよく耳にする生産性は、主に「付加価値労働生産性」を指します。
これは、「労働者1人当たり」または「労働時間1時間当たり」にどれだけの付加価値を生み出せるかを示す指標です。
付加価値とは、企業が創出する売上高や経常利益のことをいい、企業の収益性や効率性を測るうえで重要な概念です。
生産性を求める計算式
生産性の比率を求める計算式は、以下の通りです。
| 生産性 = |
産出される成果(総生産量・付加価値など) |
|
投入する資源(資金・労働力・設備・時間など) |
例えば「労働者1人あたりの生産性」は、総生産量を労働者の人数で割って計算します。
100万円分の製品の生産を100人で達成した場合、1人あたりの生産性は1万円です。
また、「労働者1人1時間当たりの生産性」は、以下の計算式で求めます。
| 生産性 = |
産出される成果(総生産量・付加価値など)÷労働者数×労働時間 |
例えば、100万円分の製品の生産を100人で2時間かけて達成した場合、1人1時間あたりの生産性は5,000円ということになります。
公益財団法人 日本生産性本部による「日本の労働生産性の動向 2023」によれば、2022年度の日本の時間当たりの名目労働生産性(就業1時間当たり付加価値額)は5,110円でした。
もちろん、生産性の数値は業種や企業によって異なりますが、この金額を目安として捉えると、自社の課題が見えてくるのではないでしょうか。
生産性向上はなぜ必要?3つの目的

生産性向上は、企業の持続的な成長と競争力を維持するために不可欠な取り組みです。
ここでは、企業が生産性向上に取り組むべき理由として、主な3つの目的を紹介します。
国際的な競争力強化
公益財団法人日本生産性本部が公表したデータによると、日本の労働生産性は他国と比較して低めとされています。
例えば、2022年において1時間当たりの労働生産性を比較した結果、OECDに加盟する38ヶ国のうち、日本は30位という低い順位となりました。
また、一昔前まで高い評価を受けていた日本の製造業生産性も、2021年においてはOECD 34ヶ国中18位に留まっています。
この状況は、日本企業がグローバル市場で競争するうえで不利になりつつあることを示しています。
個々の企業はもちろん、日本企業全体としての国際的な競争力を強化するためにも、生産性を向上させるための取り組みは不可欠だと言えるでしょう。
少子高齢化による労働力人口の減少
少子高齢化が進む日本では、労働力人口(15 歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)が年々減少しています。
出生数も減少しているため、今後もしばらくは労働人口減少の流れが改善する見込みは低いと言えるでしょう。
実際に、多くの企業が人材不足に悩んでいます。
企業の存続を図るためにも、労働者一人ひとりの生産性を向上させ、人材不足の影響を軽減することが急務と考えられているのです。
働き方・労働者意識の変化
近年、働き方改革や新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、従業員の働き方や意識が大きく変化しています。
多くの労働者がワークライフバランスの重視し、長時間労働や過度なマルチタスクから距離を置く傾向にあるようです。
このような変化に対応し、従業員にとって働きやすい職場環境を提供することは、企業としての魅力につながります。
優秀な人材を確保し、持続的な経営を行うためにも、ワークライフバランスの充実を目指す生産性向上は、企業にとって重要な取り組みと言えるでしょう。
厚生労働省が公表した調査結果でも、従業員満足度と顧客満足度の両方を重視する企業のほうが、業績が好調であることが示されています。
生産性向上に向けた取り組みの一例

生産性を向上させるためには、少ない資源でより多くの成果を達成しなければいけません。
ここでは、実際に効果的な生産性向上の取り組み事例をいくつか紹介します。
タスク管理の可視化
効率的にプロジェクトを進行させるためには、タスクの管理とその進捗を可視化することが重要です。
タスクの進捗状況をリアルタイムで把握できれば、必要に応じて業務負担の調整が可能となります。
また、今まで「見えなかったもの」が「見える」ようになるだけで、労働者の意識が変わり、生産性が向上することも多いです。

例えば「Jira」は、世界で65,000を超える企業で利用されているグローバルスタンダードなタスク管理ツールです。
ロードマップ機能でプロジェクトの全体像を視覚的に把握できるほか、カンバンボードやスクラムボード、ダッシュボードなど、さまざまな機能が用意されています。
システム開発現場向けのプロジェクト管理ツールですが、営業チームやバックオフィス部門など、幅広いビジネス現場に導入が可能です。
定型業務の自動化
単純で繰り返し行われる作業などの定型業務は、AIやアルゴリズムを活用して自動化するのが効果的です。
自動化によって時間がかかる定型業務から解放されるため、労働者はより創造的で付加価値の高い業務に注力できるため、生産性向上が見込めます。

提携業務の自動化に有効なAIツールとしては、「Linka」がおすすめです。
Linkaは対話型AIツールで、問い合わせ対応やニーズの引き出し、有益な情報の収集から提案に至るまで、さまざま業務の自動化を可能にしてくれます。
業務の標準化
システムやツールを導入し、属人化しやすいアナログ業務を標準化することも、生産性向上に向けた取り組みです。ツールを用いることで、誰でも一定の品質を保てるようになり、属人化の解消を図れます。
業務の標準化ができれば、特定のメンバーの知識・経験に頼る必要がなくなるため、生産性向上につながるでしょう。

ローコード開発プラットフォーム「Mendix」は、脱エクセルをはじめ、社内DXに有効なツールです。
プログラミングの知識がないビジネスユーザーでも社内システムやアプリケーションの開発ができるため、業務の効率化と属人化の解消をスピーディーに実現できます。

アウトソースの検討
限られたリソースの中で最大の成果を出すためには、外部の専門業者に業務を委託するアウトソーシングの検討も重要です。
特に、コア業務以外の周辺業務、定型作業だけれども専門知識が必要な業務は、アウトソースをしたほうが生産性向上につながるケースもあります。

例えば「ジョーシス」は、意外と手間のかかる入退社業務のアウトソーシングが可能です。
デバイス購入&リースやキッティング、PCの回収・保管・廃棄まで、情報システム部門の繰り返し作業をすべて外部リソースに任せることができます。
また、SaaSアカウントの発行・削除など、コーポレートITのアナログな業務と台帳管理を自動化でき、生産性向上と同時にセキュリティ向上を実現します。
コミュニケーションの促進
従業員間のスムーズなコミュニケーションは、チーム全体の生産性向上に欠かせない要素です。
テレワークやリモートワークが普及するなか、ビジネスチャットツールの導入は必要不可欠と言っても過言ではありません。

例えば「Mattermost」は、クラウド利用だけでなくオンプレミスでも利用できるチャットツールです。
プラグインの導入により、自社に合わせたカスタマイズができるというメリットもあり、生産性向上を目指す企業におすすめです。
生産性向上が企業にもたらすメリットは?

生産性向上にはデジタル化やITツールの活用が不可欠であり、導入時には費用や手間がかかるというデメリットもあります。
しかし、企業の生産性が向上すれば、それを上回る大きなメリットが得られるはずです。
ここからは、生産性向上が企業にもたらす3つのメリットを紹介します。
企業の競争力向上
生産性の向上は、企業の競争力を高めるための取り組みです。
生産量の増加や生産スピードの加速はもちろん、業務効率化によって市場への迅速な対応、ニーズに合った製品・サービスのスピーディーな提供が可能となります。
顧客満足度を高めることができ、市場での競争優位性を確立できるでしょう。
業績が向上すれば、その利益を再投資して新たなビジネスの開発や事業拡大も促進できるため、付加価値の創出、持続的な成長の実現も期待できます。
優秀な人材の確保
生産性向上に取り組み、従業員満足度も高い企業は、自然と優秀な人材を引き寄せます。
優秀な人材の確保は、企業の改革と成長をさらに加速させる鍵となるでしょう。
また、デジタル化やITツールの導入により、短時間勤務やテレワーク、リモートワーク、フレックスタイム制など、多様な働き方をとり入れやすくなります。
柔軟な働き方が可能となれば、子育てや介護などのライフイベントを理由に退職する人が減るため、離職率の低下にも貢献します。
労働環境の改善
生産性向上を目指す取り組みは、従業員の労働環境の改善という視点でもメリットがあります。
デジタル化やITツールの導入により業務の自動化や効率化が進むと、従業員はより創造的で価値のある業務に集中できるようになるでしょう。
残業時間が減少すれば、企業としては人件費の削減となり、従業員としてはワークライフバランスの向上につながります。
生産性向上の目的・メリットを理解して適切なツールを導入しよう

日本が直面する少子高齢化と労働人口の減少は、企業経営にとっても大きな課題となっています。この状況を乗り越え、持続可能な企業経営を行うために、生産性向上は不可欠な取り組みです。
生産性が向上すれば、従業員満足度や顧客満足度を高めることにもつながるため、企業競争力を強化するうえでも非常に重要です。各企業にとどまらず、日本全体の生産性が向上すれば、国際競争力を高めることにもつながるでしょう。
人材不足が深刻化している日本では、システムITツールの導入・活用が生産性向上の要であるとされています。
株式会社野村総合研究所(NRI)のasleadでは、企業の生産性向上を目的とした先進的なシステムやITツールの導入をサポートしています。
選定から導入、運用の各段階にわたって専任の担当者がサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
RECOMMEND
ーおすすめ記事ー